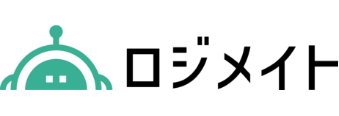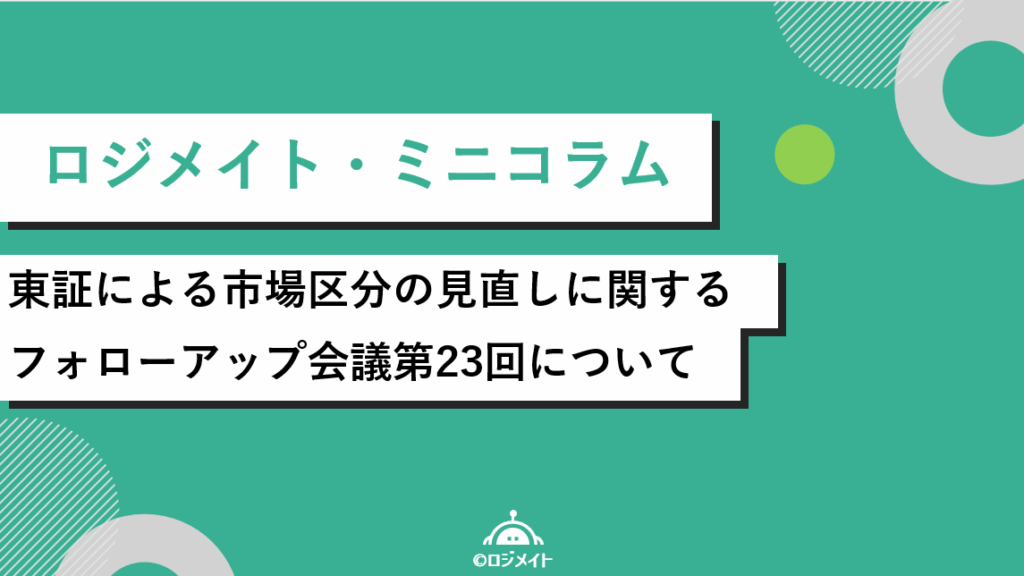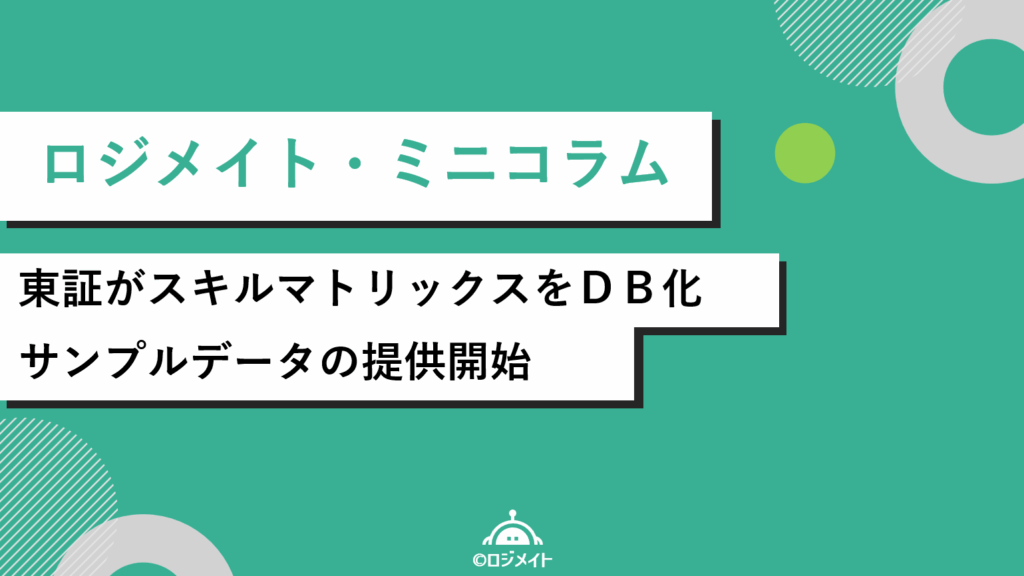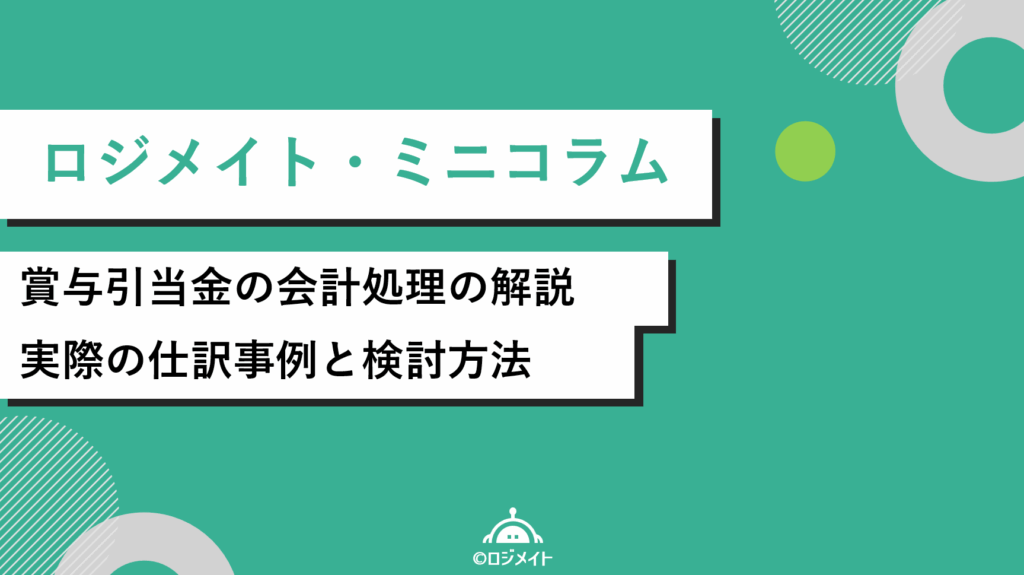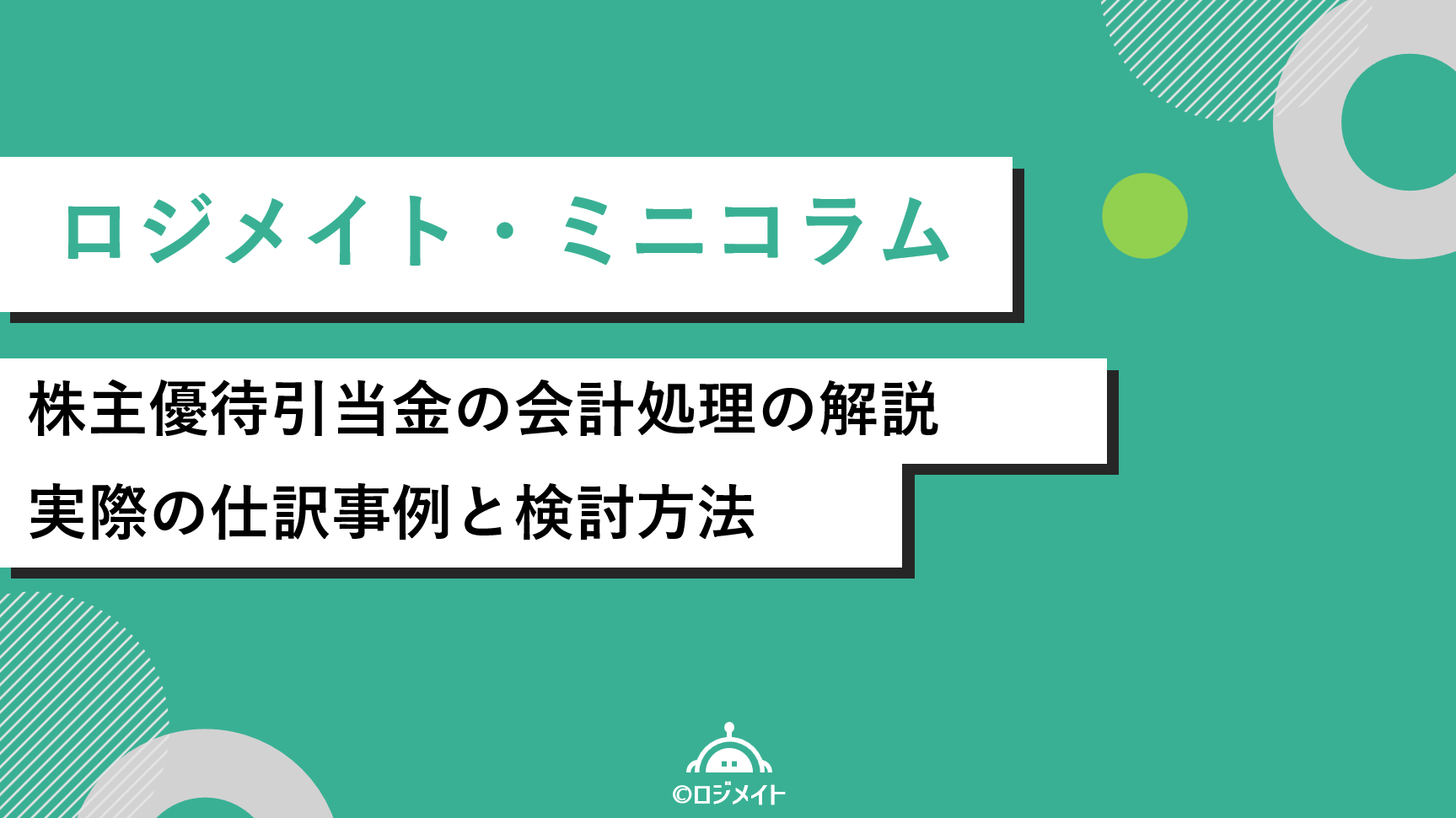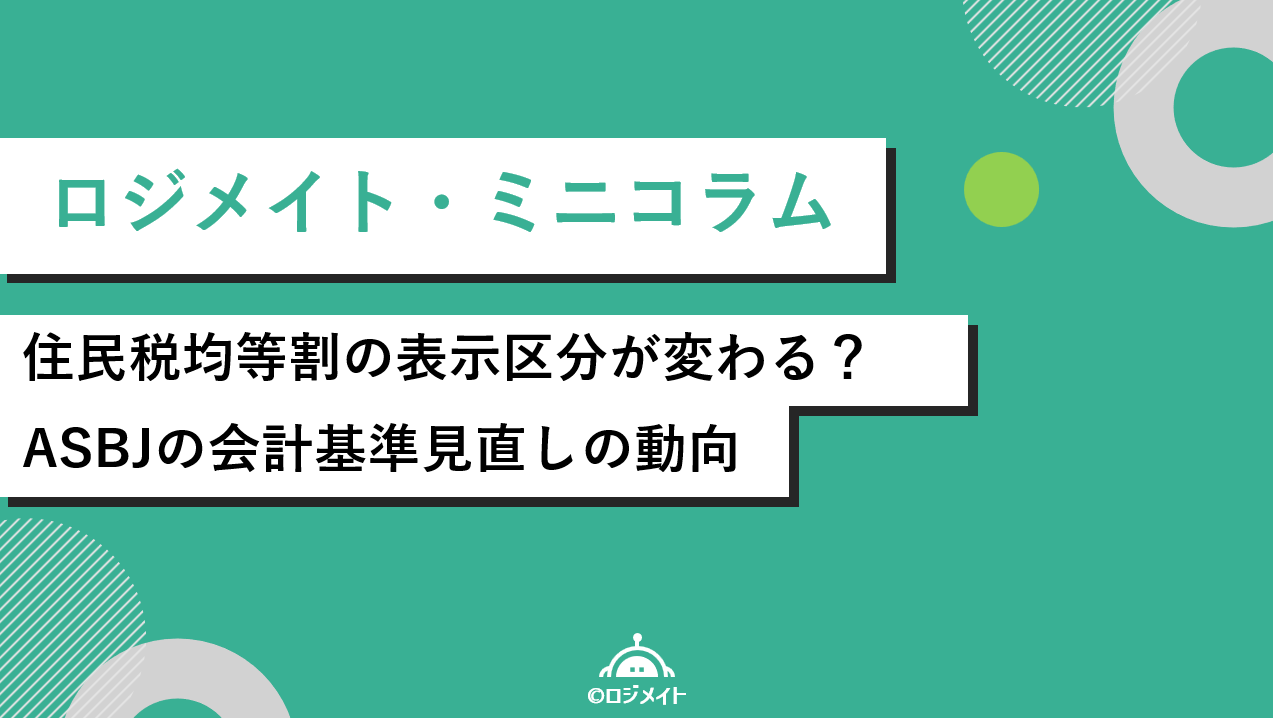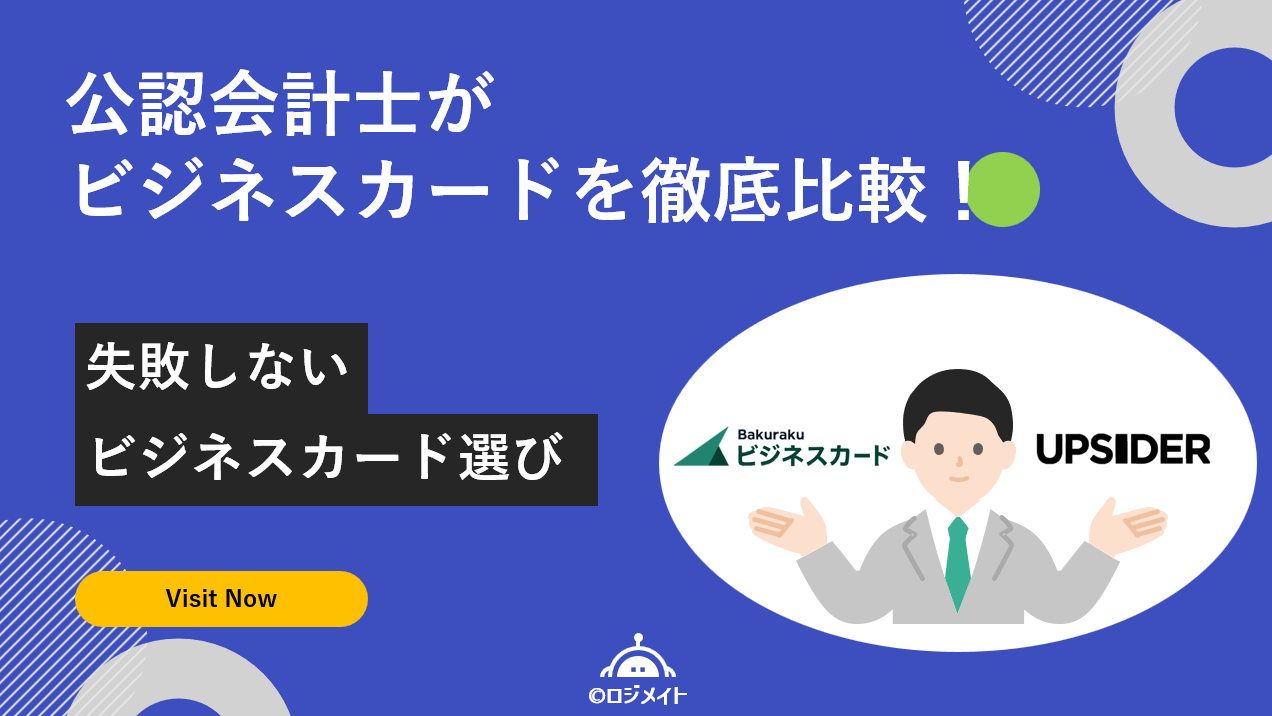ミニコラム 制度解説 制度解説_会社法
過去の誤謬を発見したら?| 過年度遡及処理と会社法の対応方法を公認会計士が解説
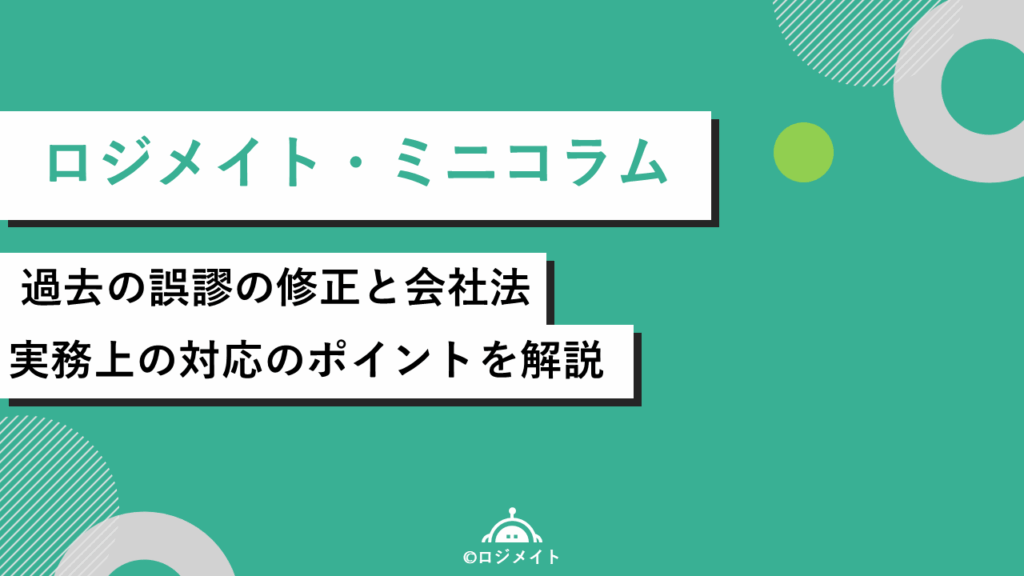

目次
Last Updated on 2025年9月2日 by ロジメイト編集部
過去の誤謬を発見したら?| 過年度遡及処理と会社法の対応方法を公認会計士が解説
はじめに
企業の会計処理において、過去の誤謬(ミス)が発見されることは決して珍しいことではありません。重要なのは、その誤謬を発見した際に、会計上および法律上どのような対応が必要になるかを正しく理解することです。
本記事では、過去の誤謬が発見された場合の対応について、会計処理と会社法の両面から解説します。特に、以下の点を中心に説明していきます。
-
過年度遡及処理という会計処理方法
-
会社法上の計算書類の確定への影響
-
誤謬の重要性の判断基準
過去の誤謬とは
過去の誤謬に対して必要な対応
過去の誤謬とは、計算書類の作成時点で利用可能だった情報を使用しなかった、または誤用したことから生じる誤りのことです。
誤謬が発見された場合、2つの対応が必要になります。
-
これから作成する当期の計算書類での対応
-
すでに作成した過年度の計算書類での対応
重要性の2つの基準
誤謬への対応を決める際、2つの「重要性」を考える必要があります。
-
会計上の重要性:投資家の判断に影響するレベル
-
会社法上の重要性:株主総会の承認をやり直すほど重大なレベル
なお、一般的には会計上の重要性よりも、会社法上の重要性の方がハードルが高いものと考えられております。
なぜ会社法上の重要性の方がハードルが高いのか
会社法上の重要性の方が、より高いハードルとなることが一般的です。これは以下の理由によります。
①法的効果の重大性
会計上重要な誤謬は、財務諸表の修正再表示で対応可能です。
一方、会社法上重要な誤謬は、当時計算書類を承認した株主総会決議が無効となり、すべての手続きをやり直す必要があります。
②実務的な影響の違い
会計上の修正については、投資家への情報提供として修正版を開示すれば足りることが多いです。
一方、会社法上の修正は過去の配当や役員報酬の決議まで遡って無効となる可能性があり、その影響範囲が広く、大きいものとなります。
③判断基準の違い
会計上の重要性は、一般には投資判断に影響する程度(一般的に税引前利益の5%程度が目安)といわれております。
一方で会社法上の重要性は株主総会の意思決定を覆すほどの重大性(配当可能額の算定に重大な影響等)がある必要があります。
例えば、税引前利益1億円の会社で600万円の誤謬があった場合、会計上は重要(6%)と判断される可能性が高いですが、仮に配当可能額を10億円とした場合、これに対しては0.6%の影響しかないため、会社法上は重要でないと判断される可能性があります。
このため、多くの誤謬は「会計上は重要だが、会社法上は重要でない」という結論になり、財務諸表の修正再表示は行うものの、過去の株主総会決議は有効なまま維持されることが一般的です。
このような理由から、会社法上の重要性の方が、より高いハードルとなることが一般的です。
過去の誤謬について、当期の計算書類での対応
基本的な処理方法
過去の誤謬が見つかった場合、当期の計算書類では、
当期の期首残高 = 前期末の残高 + 過去の誤謬の累積影響額
となるように処理を行います。
この方法により、過年度の計算書類や会計帳簿そのものは修正せず、当期の期首残高で調整することになります(会社計算規則96条7項1号)。
具体的な会計処理の例
ケース:3年前(X1年度)に固定資産の減価償却費を300万円過少計上していたことが当期(X4年度)に判明
誤謬の累積影響額の計算
-
X1年度の減価償却不足:300万円
-
X2年度の減価償却不足:300万円
-
X3年度の減価償却不足:300万円
-
累積影響額:900万円
当期(X4年度)の仕訳
期首(修正仕訳):
利益剰余金(期首) 900万円 / 減価償却累計額 900万円
→過去の影響を期首にて反映する。
当期の通常の減価償却:
減価償却費 300万円 / 減価償却累計額 300万円
注記での開示例
「過年度の減価償却費の計上に誤謬があったため、当事業年度の期首における利益剰余金の残高を900万円減額しております。」
会計処理のポイント
以下が過去の誤謬に関する会計処理のまとめです。
- 過年度の帳簿は修正しない:すでに確定した過去の会計帳簿や計算書類は変更しません
- 期首残高で一括調整:累積的な影響額をすべて当期の期首で調整します
- 比較情報の修正再表示:前期の比較情報は修正後の数値で表示します
- 適切な注記:誤謬の内容と影響額を注記で開示します
各年度での処理イメージ
X1年度に誤謬が発生し、X4年度に発見された場合
| 年度 | 状況 | 処理 |
|---|---|---|
| X1年度 | 誤謬発生(未発見) | そのまま確定 |
| X2年度 | 誤謬の影響継続(未発見) | そのまま確定 |
| X3年度 | 誤謬の影響継続(未発見) | そのまま確定 |
| X4年度(当期) | 誤謬を発見 | 期首残高に累積影響額を反映 |
| X5年度以降 | 修正済み | 正常な状態で継続 |
重要な誤謬の場合、X1〜X3年度の計算書類は法的に「確定していない」可能性がありますが、X4年度以降は適切に処理することで、過去の影響から切り離すことができます。
過去の計算書類での対応
「修正」という概念はない
会社法上、過去の計算書類には「修正」という概念がありません。計算書類は確定している(有効)か確定していない(法的に無効)のどちらかです。
重要な誤謬があった場合
会社法上重要な誤謬があった場合、その計算書類は「確定していない」ことになり、以下の手続きが必要です。
①会計帳簿の修正
-
過年度の会計帳簿から遡って修正作業を実施
-
総勘定元帳、補助簿等すべての関連帳簿を修正
-
修正後の会計帳簿に基づいて計算書類を再作成
②監査手続きのやり直し
会計監査人設置会社の場合:
-
会計監査人による監査を改めて実施
-
新たな会計監査報告書の作成(監査意見の表明)
-
監査役(監査委員会)への監査報告書の提出
監査役設置会社の場合:
-
監査役による計算書類の監査
-
新たな監査報告書の作成
-
取締役会への監査結果の報告
③取締役会での承認
-
修正後の計算書類を取締役会で承認
-
定時株主総会への提出議案の決定
-
株主総会招集通知への添付書類の準備
④株主総会での承認
-
招集通知の発送(原則として総会の2週間前まで)
-
修正後の計算書類を招集通知に添付
-
誤謬の内容と修正理由の説明資料を準備
-
株主総会で特別決議または普通決議により承認
上記の流れを図示すると以下の通りです。
- 1.会計帳簿の修正
- 会計帳簿や計算書類の修正を行う
- 2.会社法監査手続きのやり直し
- 会計監査人設置会社や監査役設置会社の場合、監査手続きを再度実施する。
- 3.取締役会での承認
- 修正後の計算書類を取締役会で承認
- 4.株主総会での承認
- 修正後の計算書類を株主総会で承認
対応完了
関連する決議の見直し
なお、過去の誤謬により影響を受ける可能性がある事項は以下の通りです。
過去の誤謬により影響を受ける事項
-
配当決議:違法配当となっていた場合は返還請求の可能性
-
役員報酬決議:業績連動報酬等の再計算が必要な場合
-
役員選任決議:計算書類の虚偽記載を理由とする責任追及の可能性
その他の対応
また、その他の対応としては以下の通りです。
-
債権者への通知:必要に応じて主要債権者(銀行など)への説明
-
税務申告の修正:法人税等の修正申告または更正の請求
-
有価証券報告書の訂正:上場会社の場合は訂正報告書の提出
-
適時開示:東証等への適時開示(上場会社の場合)
これらすべての手続きを完了させることで、初めて過去の計算書類が法的に「確定」したことになります。手続きには相当な時間とコストがかかるため、誤謬の会社法上の重要性判断は慎重に行う必要があります。
重要でない誤謬の場合
会社法上重要でない誤謬の場合、過去の計算書類は確定済みとして有効です。ただし、参考情報として修正版を提供することは可能です。
誤謬の重要性をどう判断するか
計算書類の確定を妨げるほどの「重要性」について、裁判例は以下のような判断基準を示しています。
大阪地判昭和44年7月8日(民集8巻705頁)
この判例では、計算書類の根幹に関わる誤謬や、株主の判断に重大な影響を与える誤謬は、計算書類の確定を妨げるとしています。つまり、形式的な誤りではなく、株主が承認するかどうかの判断を左右するような実質的な誤謬が重要とされます。
東京地判昭和29年11月11日(判タ43号58頁)
配当可能利益の算定に影響する誤謬は重要とする一方で、形式的な誤謬は必ずしも確定を妨げないとしています。これは、配当という株主の直接的な利害に関わる事項への影響を重視した判断です。
大阪地判昭和44年3月26日(判タ235号253頁)
誤謬の金額的重要性だけでなく、質的重要性も考慮すべきとしています。また、業界慣行や会社規模も判断要素となることを示しており、画一的な基準ではなく、個別の会社の状況に応じた判断が必要であることを示唆しています。
実務上の判断ポイント
これらの判例から、以下の要素を総合的に考慮して重要性を判断することになります。
-
株主の意思決定への影響:その誤謬を知っていたら株主は承認しなかったか
-
配当可能額への影響:分配可能額の算定に重大な影響があるか
-
金額的重要性と質的重要性:金額の大小だけでなく、誤謬の性質も考慮
-
会社の規模や業界慣行:同規模・同業他社での一般的な取扱いとの比較
ただし、文書でも指摘されているように「裁判例からも一般的な基準を導き出すのは困難」であり、最終的には個別事案ごとの慎重な判断が必要となります。
まとめ
過去の誤謬への対応は、単なる会計処理の問題ではなく、会社法上の重要な問題です。
ポイントをまとめると以下の通りとなります。
-
当期の計算書類では、期首残高で調整する(過年度遡及処理)
-
過去の計算書類は、重要性により「確定している」か「していない」かを判断
-
重要な誤謬の場合、確定手続きをすべてやり直す必要がある
適切な対応により、過去の誤謬の影響を最小限に抑えることができるでしょう。なお、
バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!
記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!
ロジメイトの特徴
-
公認会計士による専門的なサポート
-
企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援
-
創業期からIPO準備企業まで幅広い実績
-
自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!