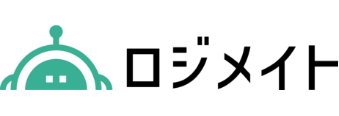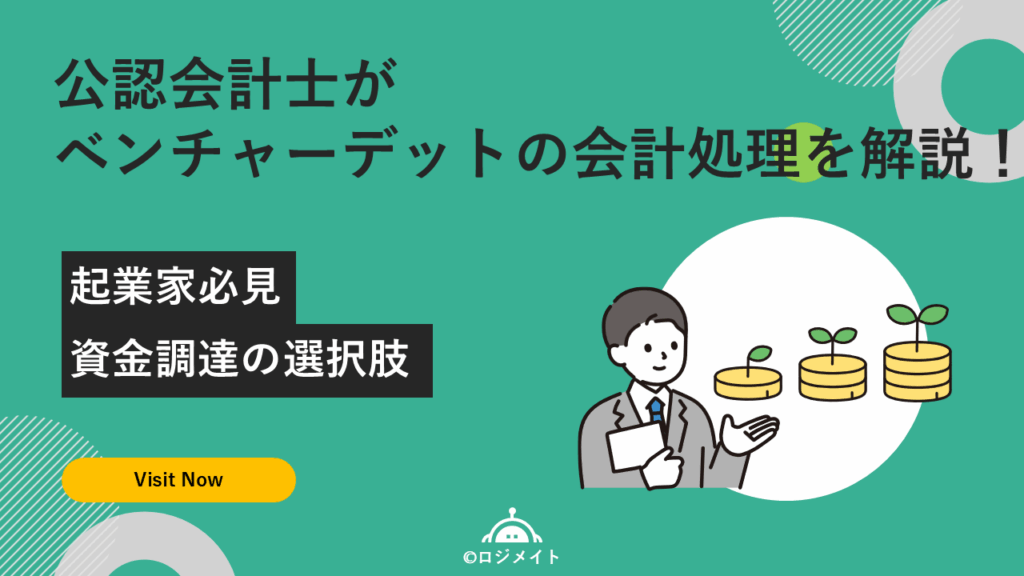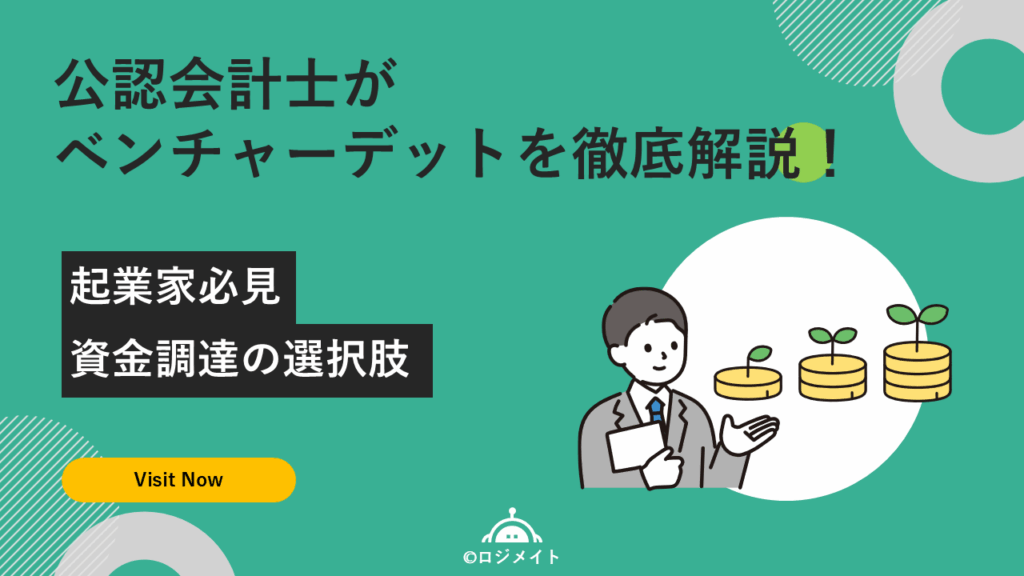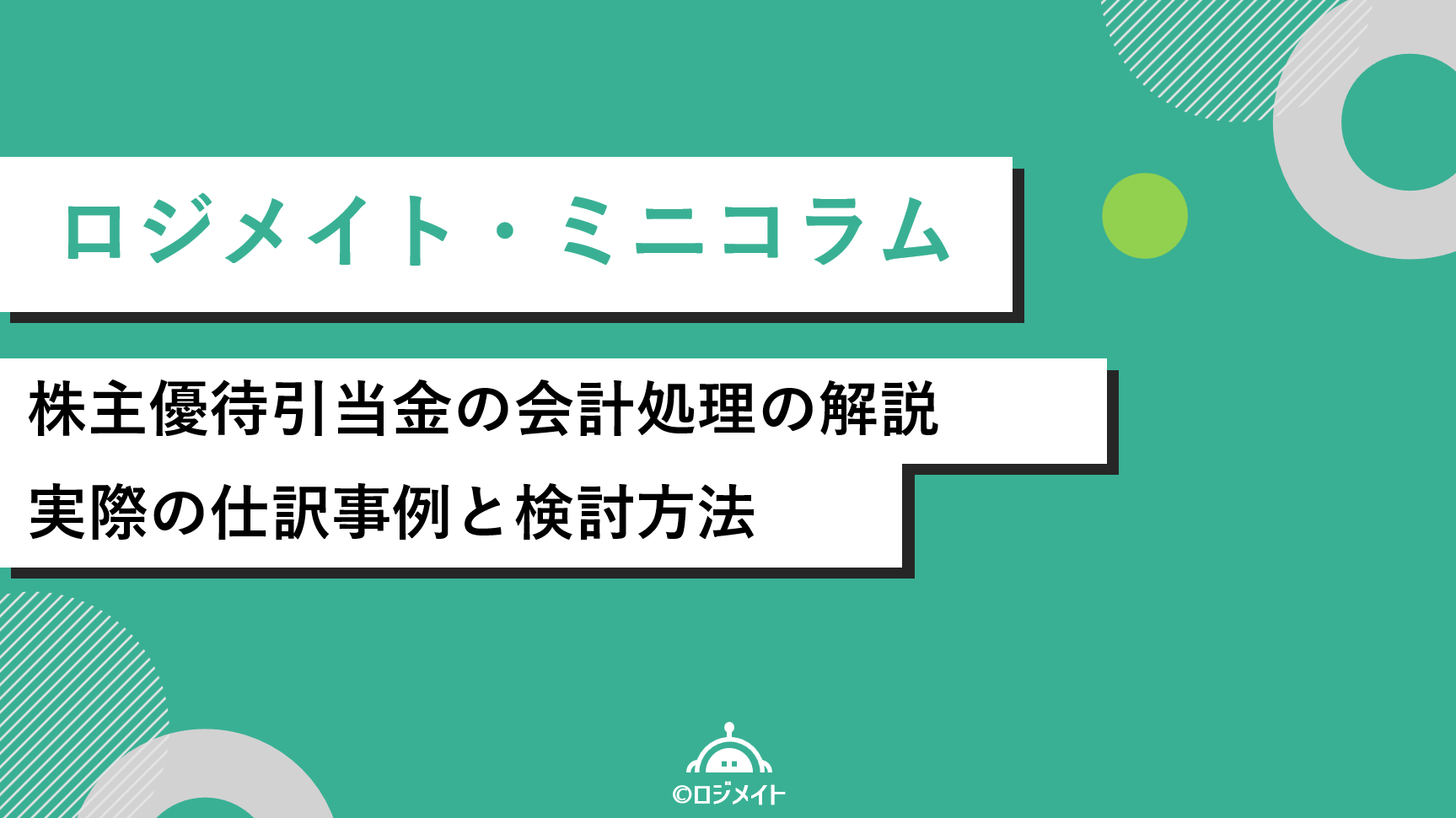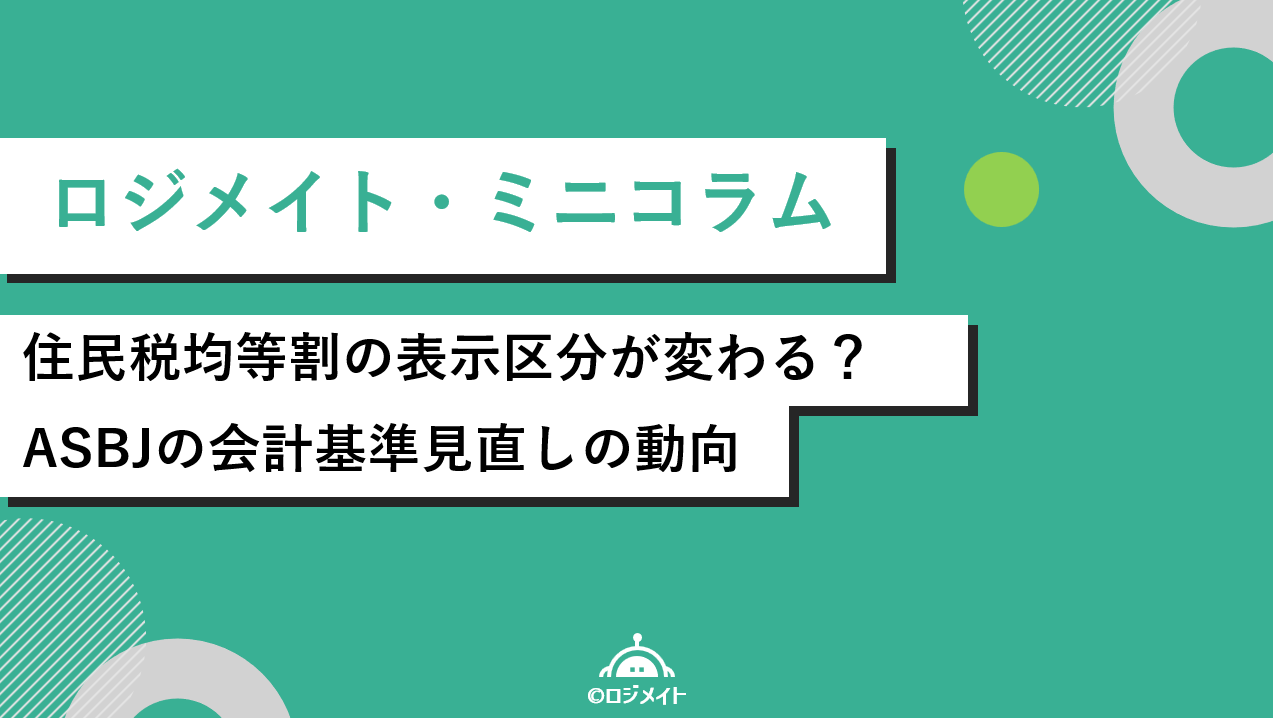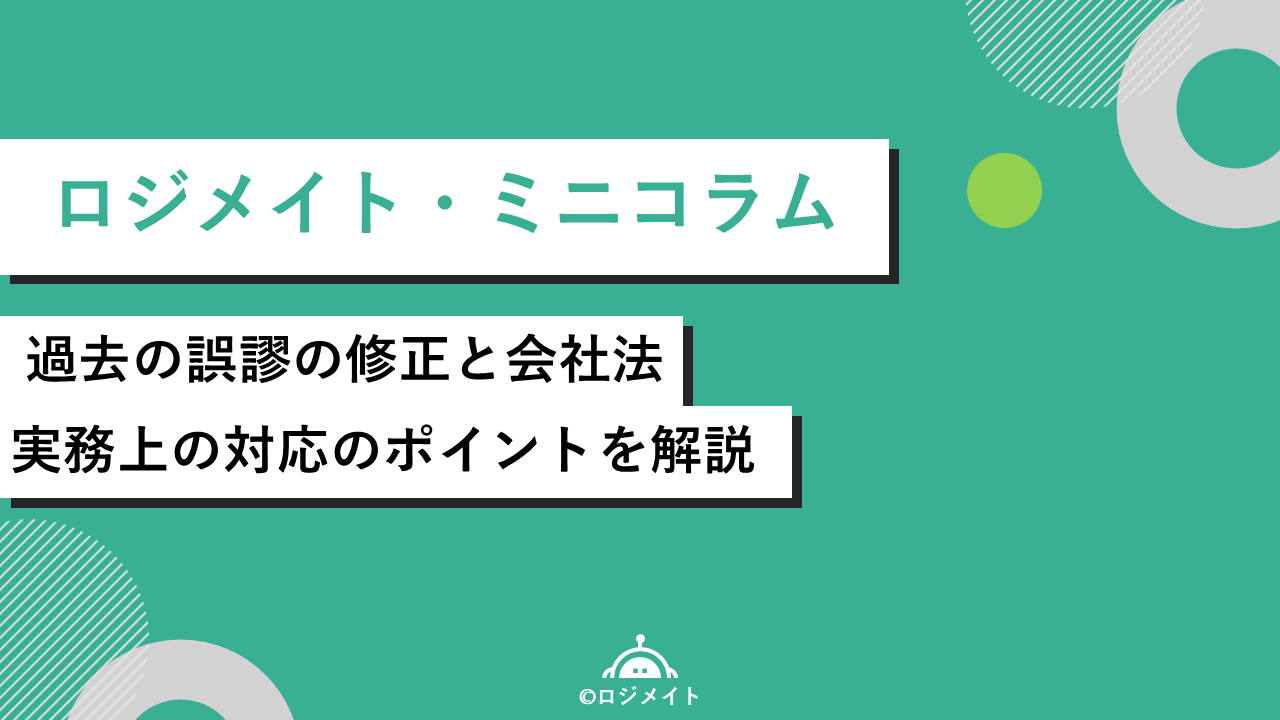財務関連
銀行との付き合い方で融資が変わる|中小企業経営者が押さえるべき審査対策銀行との付き合い方と融資対応
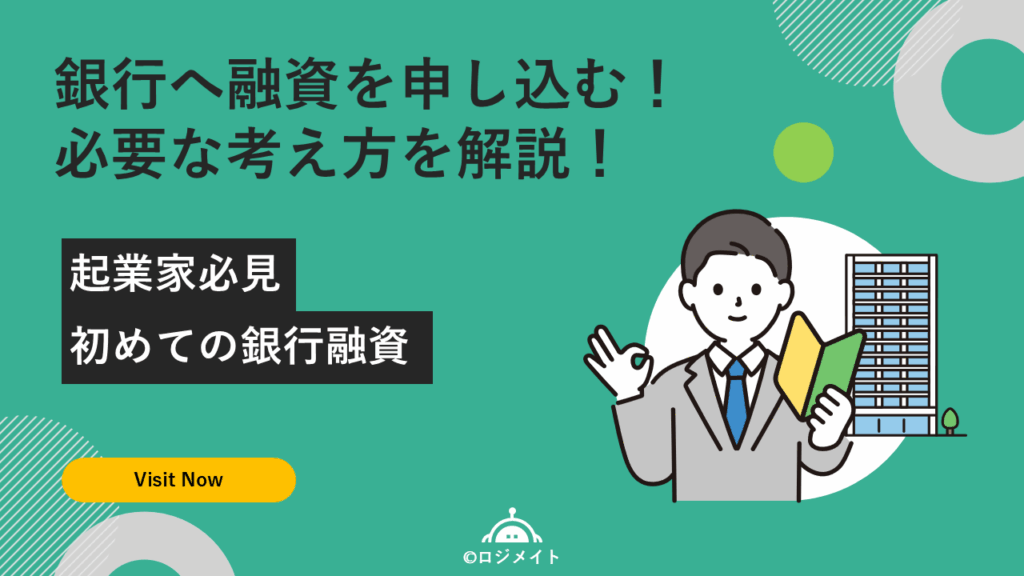

目次
Last Updated on 2025年8月5日 by ロジメイト編集部
銀行との付き合い方と融資対応
中小企業の経営者なら誰もが一度は頭を悩ませる銀行との関係。「融資を断られたらどうしよう」「どうすれば銀行に信頼してもらえるのか」といった不安を抱えている方も少なくないでしょう。この記事では、銀行との付き合い方について解説していきます。

銀行と良好な関係を築き、融資を成功させましょう!
銀行との関係はどこから始まる?

銀行との関係構築は、多くの場合、口座開設から始まります。この段階では単なる取引先の一つですが、将来的な融資ニーズがある場合は、口座開設時に「事業拡大に伴い、将来的には融資の相談もさせていただきたいと考えています」と伝えておくことで、銀行側にも意図が伝わります。
継続的な取引実績も重要な要素です。売上金の入金、給与支払い、諸経費の引き落としなど、日常的な資金の流れを通じて事業の実態を示すことができます。数ヶ月間の安定した取引があれば、銀行から事業状況についての問い合わせが来ることもあります。
関係を深める最初のきっかけは、融資相談以外の面談から始めることが効果的です。事業計画の相談や資金繰りの見通しについて意見交換したいという形で担当者との面談を設定し、会社概要や事業内容を説明する機会を作ります。

継続的な入出金履歴の積み重ねで、
事業が回っているのを示していくのが大事ですね!
銀行との関係構築が重要な理由
銀行は融資業務で収益を上げていますが、同時に貸し倒れリスクの管理も重要な課題です。そのため、財務内容だけでなく、経営者の人柄や事業への取り組み姿勢も重視します。「この会社であれば安心して融資できる」という信頼を得ることが、円滑な資金調達の基盤となります。
銀行の貸付業務において、たった1件の貸し倒れが発生するだけで、その甚大な損失を回復するためには数十件から数百件もの正常な貸付による利息収入が必要となります。例えば、年利3%の貸付で1件100万円の貸し倒れが生じた場合、同額の利益を取り戻すには実に約33年分もの利息収入を要する計算となります。このような損害リスクがあるため、銀行は極めて厳格な審査体制と徹底したリスク管理体制の構築を経営の生命線として位置づけています。
継続的な関係構築では、業績好調時だけでなく、困難な状況にある時期の対応も重要な要素となります。月次試算表の定期的な提出や、業績変動の背景説明を通じて、透明性の高いコミュニケーションを維持することで、長期的な信頼関係を築けます。

1件貸し倒れてしまうと、それを取り返すために多大な労力が必要なんですね…!
融資審査で見られるポイントを知っておこう
「うちの会社、融資審査に通るかな?」と不安に思ったら、まず銀行が何を重視しているかを理解しましょう。審査のポイントは実はそれほど複雑ではありません。
融資申請を行う際には、銀行の審査基準を理解した上で適切な準備を行う必要があります。銀行は主に以下の三つの観点から融資判断を行います:
融資判断の観点
-
返済能力:売上高、利益率、キャッシュフローなどの財務指標
返済能力の評価では、単年度の業績だけでなく、過去3年程度の業績推移を重視します。売上が安定しているか、利益率に大きな変動がないか、借入金の返済原資となるキャッシュフローが十分に確保できているかが詳細に検証されます。特に債務償還年数(BS上の有利子負債÷単年度のキャッシュフロー)は重要な指標とされ、一般的に10年以内であることが望ましいとされています。 -
担保・保証:不動産担保や信用保証協会の保証の有無
担保・保証については、無担保融資の場合でも信用保証協会の保証を活用することで融資を受けやすくなります。不動産担保がある場合は担保価値の査定が行われ、融資額の上限が決まります。代表者保証については、最近は経営者保証に関するガイドラインにより、一定条件下では保証を求めない融資も増えています。 -
資金使途の妥当性:借入資金の具体的な使用目的と効果
資金使途の妥当性では、設備資金と運転資金で審査のポイントが異なります。設備資金の場合は、導入する設備の必要性、投資効果、回収期間などが重要視されます。見積書や設備仕様書、投資計画書の提出が求められることが多く、設備導入により売上増加や効率化がどの程度見込めるかを具体的に説明する必要があります。運転資金の場合は、資金繰り表による必要資金の算定根拠と、売掛金や在庫の回転期間などの妥当性が審査されます。
決算書の数字だけ見て「あ、ダメかも」と諦める必要はありません。大切なのは現状をきちんと把握し、銀行に対して筋の通った説明ができるかどうかです。例えば、売上が下がっていても「コロナの影響で一時的に落ち込んだが、新規開拓により回復基調にある」といったような具体的な説明があれば、銀行側も納得しやすくなります。
資金繰り表や事業計画書も重要ですが、あまりに右肩上がりすぎる計画は逆に不自然に映ることがあります。現実的な数字で、しっかりと根拠を示すことの方がよほど重要です。例えば、設備投資の場合は「なぜその設備が必要なのか」「導入後どの程度の効果が見込めるのか」を具体的に説明できるよう準備しておきましょう。

「どのように返済していくか」しっかり示していきましょう!
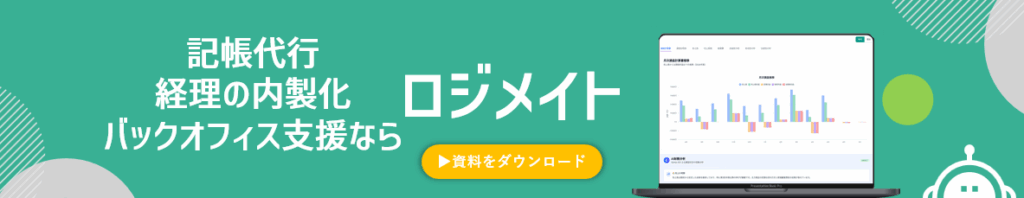
銀行の担当者とどう付き合うか
銀行の担当者も人間です。「この社長なら応援したい」と思ってもらえるかどうかが、融資成功の大きな分かれ目になります。堅苦しく構える必要はありませんが、相手の立場を理解した対応を心がけることが大切です。
担当者は社内で融資案件を説明する際、「この会社は信頼できる」と上司に報告する必要があります。そのための材料を提供するのが経営者の役割。業績の良し悪しに関わらず、現状と今後の見通しを率直に伝えることで、担当者も安心して案件を進められるようになります。
意外と見落としがちなのが担当者の異動です。銀行では2〜3年で担当者が変わることが珍しくありません。新しい担当者には改めて自社の概要や強みを説明し、これまでの取引経緯についても丁寧に伝えましょう。最初の印象で今後の関係が決まることも多いので、この機会を軽視してはいけません。
銀行との付き合いは、結局のところ「人と人との関係」に行き着きます。完璧な財務諸表を作ることも大切ですが、それ以上に誠実な対応と継続的なコミュニケーションが成功の分かれ目となります。一度信頼関係ができてしまえば、多少の業績悪化があっても相談に乗ってもらえるものです。焦らず、長期的な視点で関係を築いていくことが、安定した資金調達への近道と言えます。

金融機関の担当者を味方につけましょう!
融資を受けるためには誠実な姿勢が、何よりも大切ですね!
「メインバンク一本」は本当に正解か?

昔から「メインバンクとは長く付き合うべき」と言われますが、最近は複数の金融機関と取引する企業が増えています。これには合理的な理由があります。
メインバンクとの関係を重視しつつも、複数の金融機関との取引を維持することは、資金調達の安定性向上において有効な戦略です。多様な金融機関とのネットワーク構築により、以下のようなメリットが得られます:
融資判断の観点
-
地方銀行:地域密着型のきめ細かいサービスと柔軟な対応
地方銀行は各都道府県に本店を置く普通銀行です。地方銀行は地域経済の活性化を使命としており、地元企業への融資に積極的な姿勢を示しています。大手都市銀行では採算が合わない小口融資や、地域特有の事業に対する理解も深く、経営者との距離が近いことが特徴です。また、地域の商工会議所や自治体との連携も強く、補助金情報や地域イベントへの参加機会なども提供してくれます。 -
信用金庫:中小企業支援に特化した制度と親身なサポート
信用金庫は信用金庫法に基づく会員制の協同組織金融機関です。株式会社である銀行とは異なり、営利追求よりも地域貢献を重視した経営を行っています。会員資格は中小企業や個人に限定されており、大企業は利用できません。そのため、財務内容だけでなく地域への貢献度や将来性を総合的に判断する傾向があります。創業支援や事業承継、経営改善支援などの相談機能も充実しており、単なる資金提供者を超えた経営パートナーとしての役割を果たしています。 -
政府系金融機関:長期・低金利融資や創業支援制度の充実
政府系金融機関では、日本政策金融公庫が最も代表的です。民間金融機関を補完する役割を担っており、創業融資、小規模事業者向け融資、設備投資促進融資など、政策目的に応じた多様な制度融資を用意しています。金利も比較的低く、返済期間も長期間設定できることが多いため、設備投資や事業拡大時の資金調達において重要な選択肢となります。商工中金(商工組合中央金庫)も政府系金融機関として、中小企業の協同組合やその組合員に対する融資業務を行っています。
複数行取引のもう一つのメリットは、金融機関同士の競争原理を活用できることです。融資条件の比較検討が可能になり、より有利な条件での資金調達が期待できます。ただし、取引の分散により各行との関係が希薄になるリスクもあるため、バランスを考慮した取引配分が求められます。
このように異なる特性を持つ金融機関とのネットワークを構築することで、事業ステージや資金ニーズに応じた最適な融資を受けやすくなります。

様々な金融機関に依頼してみましょう!
特に、その地域に根ざした金融機関との関係性は重要ですね!
返済で信用を積み上げる
「借りたお金をきちんと返す」これは当たり前のことですが、実はここにも銀行との関係を良くするヒントが隠れています。
約定通りの返済を続けることはもちろん大切ですが、余裕がある時の繰上返済も効果的です。「資金に余裕ができたので、少し多めに返済します」と連絡すると、銀行側は「この会社は資金管理がしっかりしている」と評価してくれます。
逆に返済が厳しくなった時は、絶対に黙っていてはいけません。「来月の返済が少し厳しそうです」と早めに相談することで、銀行側も対応策を考えてくれます。最悪なのは、連絡もなしに返済が滞ることです。これをやってしまうと、今後の取引に大きな影響が出てしまいます。

返済は絶対に滞らないようにしましょう!
よくある質問(FAQ)
銀行に融資を申し込むのにあたって、よくある質問をまとめましたので、ご確認ください。
-
創業したばかりでも銀行からお金を借りられますか?
-
創業融資という制度があるので心配いりません。日本政策金融公庫の新創業融資制度なら無担保・無保証人で借りられますし、信用保証協会の保証付き融資も利用できます。ただし、事業計画書はしっかり作り込む必要があります。「なんとなく儲かりそう」では通りません。
-
審査にはどのくらい時間がかかるものですか?
-
だいたい1ヶ月程度と考えておけば良いでしょう。ただし、融資額が大きかったり担保が複雑だったりすると、もう少し時間がかかることもあります。急いでいる場合は最初に「いつまでに必要です」と伝えておくと、銀行側も優先的に進めてくれることがあります。
-
決算が赤字だと融資は厳しいですか?
-
赤字=融資不可ではありません。コロナ禍で一時的に赤字になった会社は数多くありますし、銀行もその辺りは理解しています。大切なのは赤字の理由と今後の改善策をきちんと説明できるかどうかです。信用保証協会の保証を使えば、赤字でも融資を受けられる可能性が高まります。
-
金利の交渉ってできるんですか?
-
長年取引していて実績があるなら、交渉の余地はあります。他の銀行の条件と比較して「A銀行はこの金利でした」と相談してみるのも一つの方法です。ただし、あまりガツガツやりすぎると関係が悪くなることもあるので、程々にしておいた方が良いでしょう。
バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!
記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!
ロジメイトの特徴
-
公認会計士による専門的なサポート
-
企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援
-
創業期からIPO準備企業まで幅広い実績
-
自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!