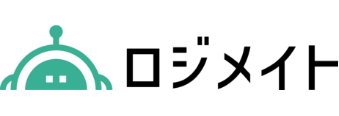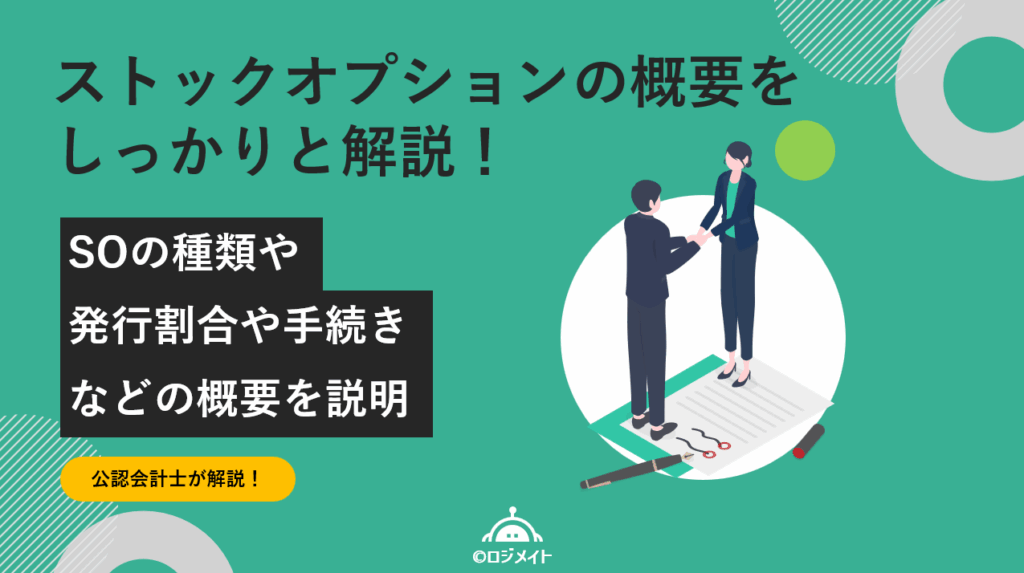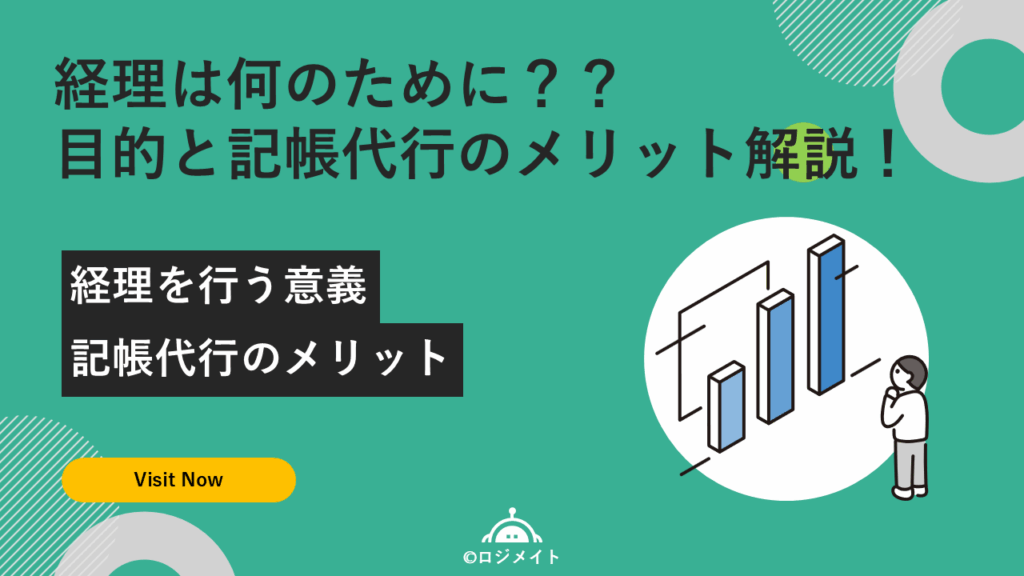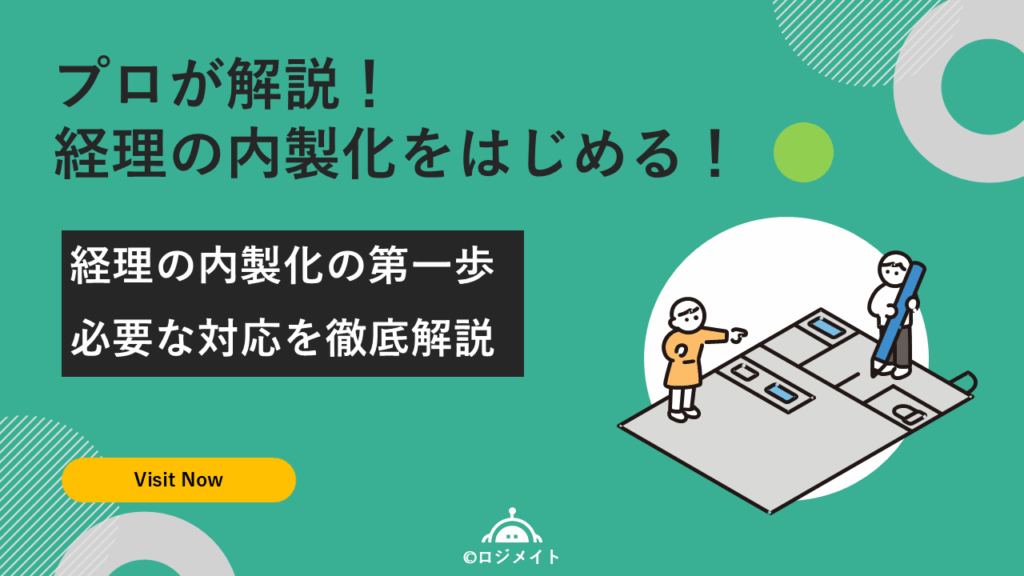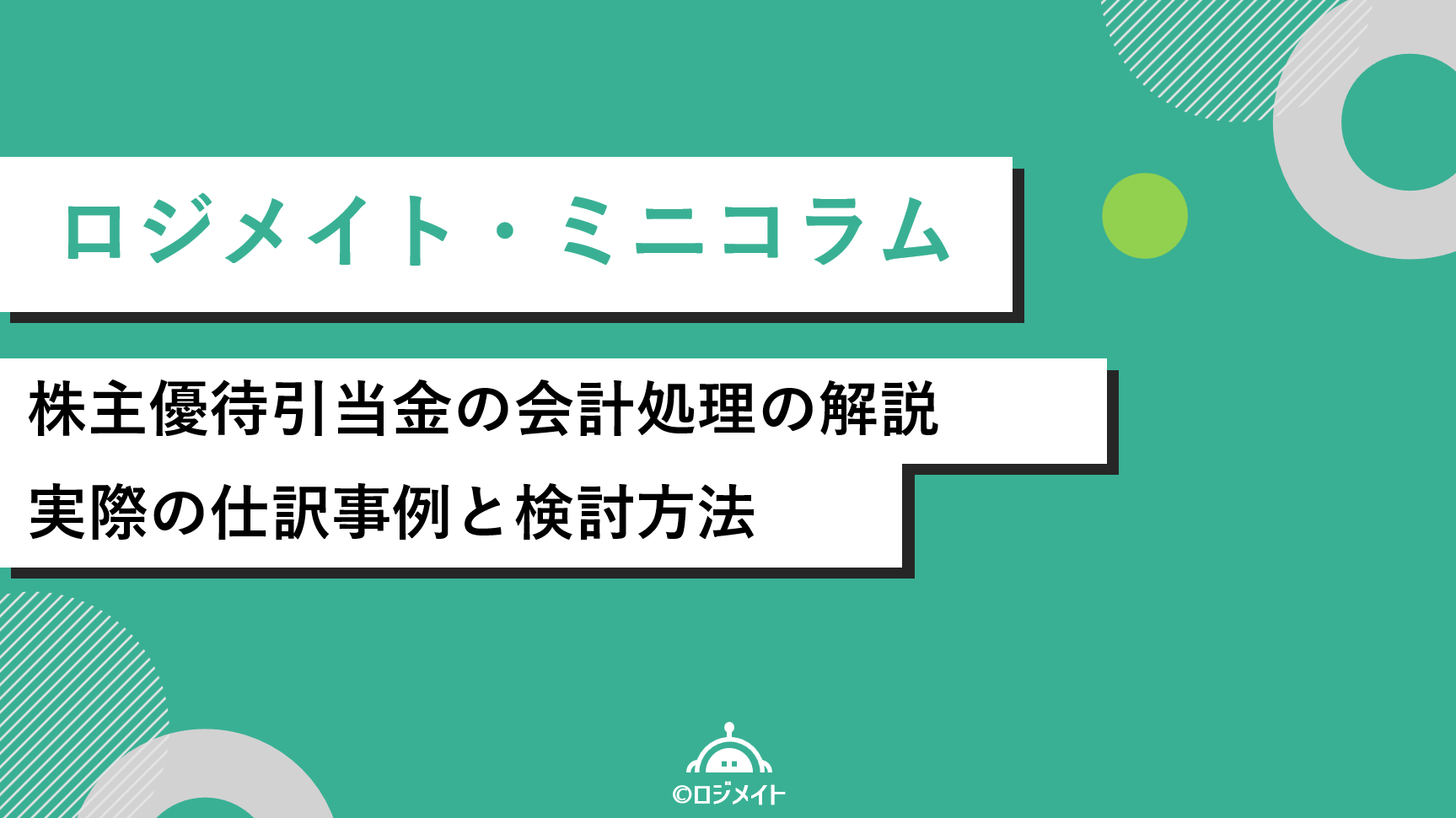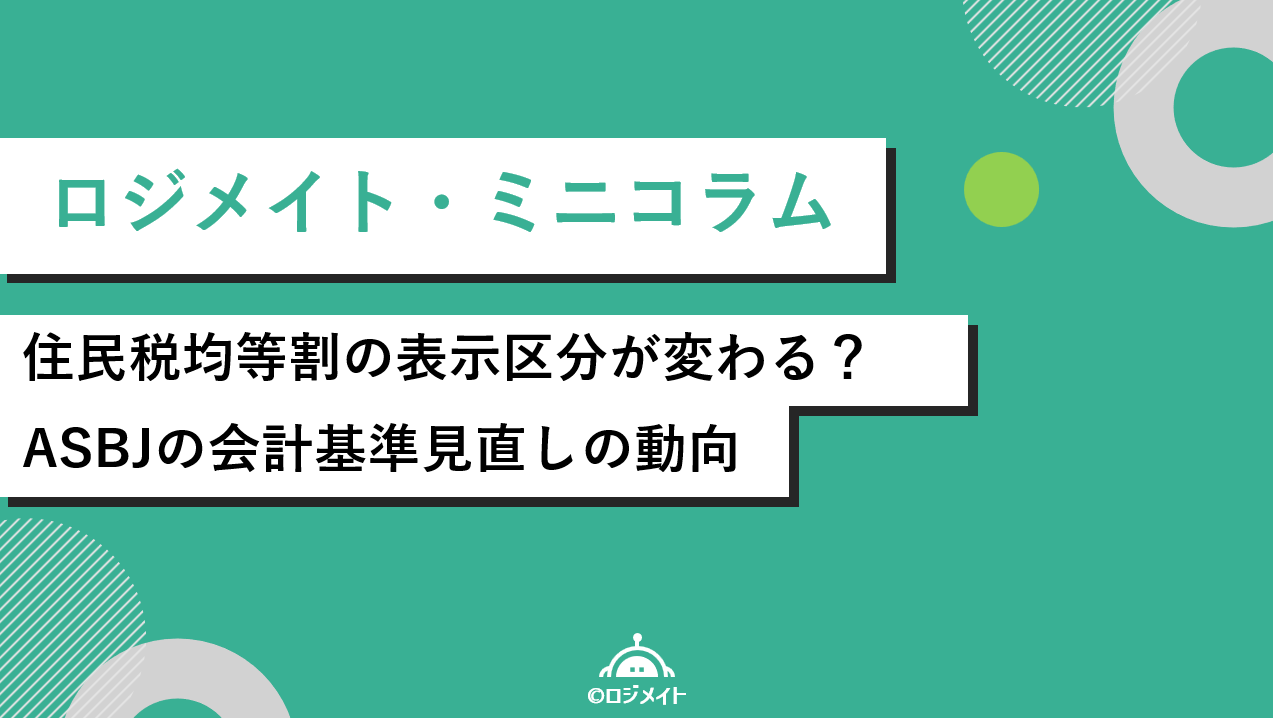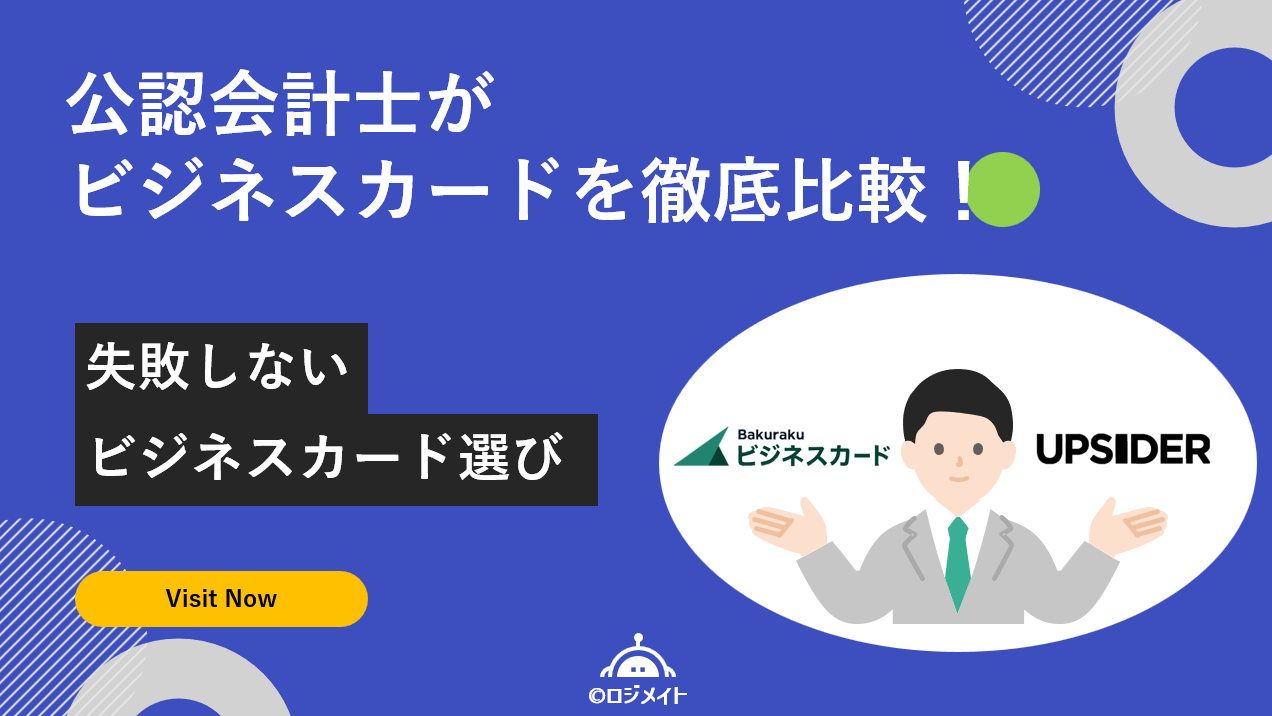バックオフィス支援
記帳代行と経理内製化の比較|メリット・デメリット・選び方を公認会計士が解説【2025年版】
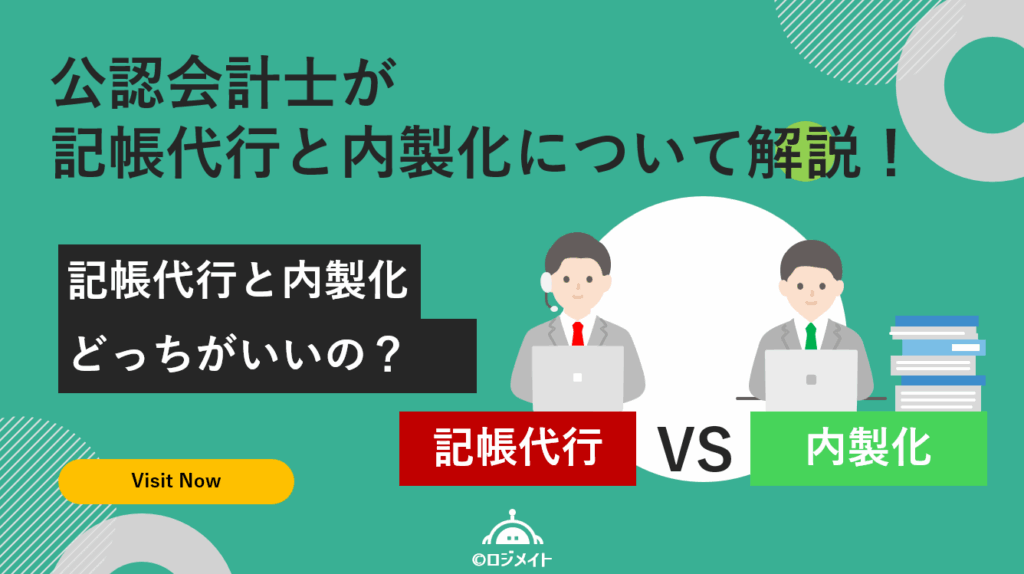

目次
Last Updated on 2025年8月5日 by ロジメイト編集部
記帳代行と経理内製化の比較|メリット・デメリット・選び方を公認会計士が解説【2025年版】
はじめに ~記帳代行?経理内製化??~
企業の経理業務において、記帳作業をどのように処理するかは重要な経営判断の一つです。外部の専門業者に委託する「記帳代行」と、社内で処理する「経理内製化」には、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。本記事では、両者を詳細に比較し、どちらを選ぶべきか考えていきます。
記帳代行とは
記帳代行とは、企業の日々の会計処理業務を外部の専門業者に委託するサービスです。
具体的には、領収書や請求書などの証憑書類の整理・仕訳、会計ソフトへの入力、試算表の作成、月次決算書の作成などの代行を依頼します。税理士事務所や会計事務所が提供することが多く、依頼者は必要な書類を渡すだけで、記帳代行業者が正確な帳簿作成を行います。近年では、クラウド会計ソフトを活用したリモート対応も可能になり、より利用しやすくなっています。
経理内製化とは
経理内製化とは、上記の記帳業務を社内の従業員が直接担当することです。
経理担当者を雇用し、会計ソフトを導入し、日々の取引を自社で記録・管理します。小規模企業では経営者自身が行う場合もあれば、専任の経理スタッフを配置する場合もあります。内製化により、企業は自社の財務状況をリアルタイムで把握でき、独自の管理方法を取り入れることが可能になります。
記帳代行に依頼するメリット・デメリット
記帳代行のメリット
記帳代行を依頼するメリットは下記のとおりです。プロに外注することで、高い効果が期待できると考えられます。
記帳代行のメリット
専門性の高いサービス
記帳代行業者は経理のプロフェッショナルです。税務に関する最新の知識を持ち、複雑な仕訳処理も正確に行えます。例えば、2023年に導入されたインボイス制度の適用判定、2024年から本格化した電子帳簿保存法への対応なども期待できます。
また、会計ソフトの操作にも精通しており、freee、マネーフォワード、弥生会計など、各種ソフトの特性を理解した効率的な処理が期待できます。一般的な経理担当者が習得に数ヶ月を要するでしょう。
即効性のあるコスト削減
社内に経理担当者を雇用する場合、給与だけでなく社会保険料、教育費用、なども発生します。年収300万円の経理担当者の場合、実際の総コストは約400万円程度が見込まれます。
一方、記帳代行の場合、月額30,000円~100,000円程度(仕訳数など作業量によって変動)で済むため、年間36万円~120万円と大幅なコスト削減が可能です。
また、経理担当者の急な退職による業務停止リスクや、補充採用コスト(求人広告費、採用面接時間など)も回避できるため、隠れたコスト削減効果も大きいといえます。
業務の標準化
記帳代行業者は多くの企業を担当しているため、業務フローが標準化されており、ヒューマンエラーが起こりにくい体制が整っています。また、複数の専門スタッフによるダブルチェック体制、最新の会計基準への自動対応など、個人や小規模チームでは実現困難な品質管理体制を活用できます。
また、担当者の体調不良や退職といった属人的リスクを回避できるのも大きなメリットです。記帳代行業者では、社内に複数の人材を抱えていることが多いため、継続的で安定した業務遂行が可能です。
本業への集中
記帳業務を外部に委託することで、経営者や従業員は売上に直結する本業により多くの時間とエネルギーを注げるようになります。特に成長期の企業にとっては、新規開拓、商品開発、マーケティングといった戦略的業務への集中が事業拡大の鍵となります。
経営者が月末の記帳作業に追われることがなくなれば、その時間を経営戦略の立案、重要な商談、人材育成などに活用できます。また、従業員も兼任していた経理業務から解放されることで、本来の業務により専念でき、生産性向上が期待できます。
これは特にスタートアップや急成長企業において、限られたリソースを最大限活用するための重要な戦略的選択といえます。

何もわからない状態では記帳代行のようなプロに頼むしかなさそうです。
ただし、プロに任せるのは一見合理的ですが、世の中そこまで上手くはいきません。以下のようなデメリットも。。。
記帳代行のデメリット
様々なメリットが考えられる記帳代行ですが、一方で以下のようなデメリットがある点を留意するべきでしょう。
記帳代行のデメリット
リアルタイムでの情報把握が困難
記帳代行の最大の課題は、リアルタイムでの財務状況把握が困難なことです。一般的に、月次での報告となるため、月中の資金繰り状況や売上動向を即座に確認することができません。これは特に、キャッシュフローが不安定な成長期の企業や、季節変動が大きい業界において、経営判断の遅れにつながるリスクがあります。
例えば、急な大口受注があった場合の運転資金の調達判断や、売上が予想を下回った場合の経費削減策の検討など、迅速な対応が必要な局面で、タイムリーな情報が得られないことは大きな制約となります。また、投資家や金融機関からの急な資料請求にも、即座に対応できない場合があります。
業務フローのカスタマイズの制約
記帳代行業者は効率性とコスト削減を重視するため、個別企業の特殊なニーズや独自の管理方法に対応できない場合があります。例えば、特殊な業界での独自の会計処理、詳細な部門別管理、プロジェクト別の原価管理など、標準的なサービスの範囲を超える要求には追加費用が発生するか、対応そのものを断られるケースもあります。
また、自社独自の管理指標やKPIに基づいた分析レポートの作成、経営陣向けの特別な資料作成なども、記帳代行の標準サービスには含まれないことが多く、本当に必要な経営情報を得るためには、結局社内での追加作業が必要になる場合があります。
解約時の引継ぎ
記帳代行を解約する際には、会計データの引継ぎが大きな負担となります。特に記帳代行業者が独自の会計ソフトやシステムを使用している場合、データ移行には専門知識が必要となり、相当な時間と労力がかかります。
さらに深刻な問題は、データの不整合や抜け漏れが発生するリスクです。長期間にわたって外部委託していた場合、社内に業務の詳細を把握している人材がいないため、引継ぎ時にエラーが発見されても、その原因究明や修正に多大な時間を要することがあります。
また、会計ソフトの乗り換えが必要な場合、過去データの変換作業、勘定科目の設定変更、取引先マスタの再構築など、システム移行に伴う様々な作業が発生し、業務に大きな支障をきたす可能性があります。場合によっては、数ヶ月間の業務停滞や、税務申告の遅延といった深刻な問題に発展することもあります。
業者による品質のばらつき
記帳代行市場は参入障壁が低いため、様々な業者が存在し、その品質には大きなばらつきがあります。税理士資格を持つプロフェッショナルから、簿記の基礎知識しかない素人まで、担当者のスキルレベルは千差万別です。
特に低価格を売りにする業者の場合、経験の浅いスタッフの起用、品質管理体制の不備、顧客サポートの不足などの問題が発生しやすく、結果として処理ミス、納期遅延、連絡不備などのトラブルにつながることがあります。
また、一部の悪質な業者では、税理士資格がないにもかかわらず「税務申告も対応可能」などと虚偽の宣伝を行い、違法行為を行っているケースも存在します。このような業者に依頼してしまうと、税務調査時に大きな問題となる可能性があるため、業者選定には十分な注意が必要です。
長期的なコスト増加
記帳代行は初期コストが安く見えますが、企業規模の拡大とともに処理量が増えれば、代行費用も比例して増加します。また、標準サービス以外の対応(急ぎ処理、特殊仕訳、詳細分析など)には追加費用が発生するため、実際の総コストは当初の見積もりを大幅に上回ることがあります。
さらに、記帳代行では対応できない業務(管理会計、予算管理、経営分析など)を別途外注したり、社内で対応したりする必要が生じると、結果的に内製化よりも高コストになる場合があります。特に成長期の企業では、こうした追加ニーズが頻繁に発生するため、長期的なコスト試算を慎重に行う必要があります。

低品質な記帳代行に依頼し、会社の数値がぐちゃぐちゃになった!業務がブラックボックス化してしまった!その結果いつまでも財務状況がわからない!というのはあるあるですね。。。
経理内製化のメリット・デメリット
経理内製化のメリット
次に、経理を内製化する際のメリット・デメリットを考えてみましょう。メリットしては以下が挙げられます。社内で経理を行うことにより、財務数値がコントロールしやすくなります。また、株式上場をするためには経理の内製化は必須となります。
経理内製化のメリット
リアルタイム経営情報の活用
経理内製化の最大のメリットは、必要な時にいつでも最新の財務状況を確認できることです。これにより、迅速な経営判断が可能になり、市場変化への対応力や競争優位性を大幅に向上させることができます。
例えば、日次での売上動向確認、週次でのキャッシュフロー把握、月中での予算進捗管理など、タイムリーな情報に基づいた機動的な経営が実現できます。これは特に、変化の激しいIT業界や季節変動の大きい小売業において、大きなアドバンテージとなります。
また、急な資金調達の必要性が生じた場合や、投資判断を迫られた場合にも、即座に正確な財務データを提供できるため、ビジネスチャンスを逃すことなく、最適なタイミングでの意思決定が可能になります。
業務のカスタマイズと最適化
内製化により、自社の業務フローや事業特性に完全に合わせた記帳方法をカスタマイズできます。業界特有の処理方法、独自の管理項目、詳細な部門別・プロジェクト別管理など、外部委託では実現困難な高度な管理が可能になります。
例えば、製造業であれば工程別の原価管理、建設業であれば現場別の収支管理、IT企業であればプロジェクト別の採算管理など、業界特性を深く理解した独自の管理手法を構築できます。これにより、一般的な財務諸表では見えない、事業の本質的な収益構造や改善ポイントを把握することが可能になります。
また、経営陣の要求に応じた独自の分析レポートや、KPIダッシュボードの作成なども、社内リソースであれば柔軟かつ迅速に対応できます。
ノウハウの蓄積
記帳業務を通じて、社内に会計・財務の専門知識とノウハウが蓄積されます。これは単なる業務処理能力の向上にとどまらず、経営品質の向上、戦略立案能力の強化、そして企業価値の向上につながる重要な資産となります。
社内に経理の専門知識が蓄積されることで、経営陣に対してより高度で実践的な財務アドバイスを提供できるようになります。また、事業計画の立案、投資判断の支援、リスク管理の強化など、経理部門が単なるコスト部門から戦略的パートナーへと進化することが可能になります。 さらに、業務改善や効率化の提案、新しい管理手法の導入なども、事業を深く理解した社内チームだからこそ実現できる付加価値といえます。
上場準備における必要性
将来的に株式上場を目指す場合、経理の内製化は避けて通れません。証券会社や取引所の上場審査では、内部統制の構築や財務報告の信頼性が厳しく評価され、自社で経理業務を管理・監督できる体制が求められます。また、月次決算の早期化や詳細な管理会計資料の作成など、上場企業に求められる高度な経理業務は、外部委託では対応が困難な場合が多いのが実情です。

自分の会社の数値を自社で作成できる、経理を内製化しているというのは、成長企業にとっては当たり前の話ですね。
経理内製化のデメリット
経理内製化には上記のようなメリットがあるものの、記帳代行という業者が存在するのには理由があります。やはり、自社で経理を内製化するまでには以下のような障壁があり、そのハードルは中々高いものとなります。
内製化のデメリット
優秀な人材確保が困難かつ高コスト
適切な経理知識と実務経験を持つ人材の確保は、現在の転職市場において困難な状況となっています。特に即戦力となる経験豊富な人材は、各企業で需要が高く、中小企業では採用コストも人件費も高騰しています。
例えば、経理経験3年以上の人材の年収は400万円~600万円が相場となっており、社会保険料等を含めた総コストは500万円~750万円に達します。さらに、採用活動にかかる求人広告費、人材紹介手数料、面接対応時間なども考慮すると、実際のコストはさらに膨らみます。
また、採用できたとしても、自社の業務に習熟するまでには3~6ヶ月程度の期間が必要であり、その間は十分な成果を期待できないという問題もあります。
業務の属人化リスク
経理内製化では、特定の担当者に業務が集中し、属人化してしまうリスクが高くなります。経理業務は専門性が高く、また企業固有の処理方法や取引先情報なども多いため、担当者以外では対応困難な状況に陥りがちです。
このような状況で担当者が急に退職した場合、業務の継続に深刻な影響を与える可能性があります。特に月末・月初の繁忙期や決算期に退職されると、業務が完全に停止してしまうリスクもあります。また、引継ぎが不十分な場合、過去の処理方法や取引先との取り決めが不明になり、後任者が大きな混乱に陥ることもあります。
さらに、担当者のスキルレベルや知識の偏りにより、処理品質にばらつきが生じる可能性も高く、継続的で安定した業務遂行の確保が困難な場合があります。
継続的な教育と研修コスト
経理業務は法令改正が頻繁に行われる分野であり、担当者は常に最新の知識を習得し続ける必要があります。これには、外部研修への参加費用、専門書籍の購入費、資格取得支援費用など、継続的な教育投資が必要です。
また、教育や研修にかかる時間も相当なものとなり、その間は通常業務への影響も避けられません。特に小規模な組織では、担当者が研修に参加している間の業務カバー体制の確保も困難で、業務停滞のリスクが高まります。
さらに、せっかく教育投資を行って担当者のスキルが向上しても、転職により他社に移ってしまえば、その投資は無駄になってしまうという問題もあります。

経理内製化のハードルは高いものの、やっぱり自社で回していけるようになるのが一番ですね!
記帳代行と経理内製化の比較表

記帳代行と経理内製化の比較表を作ってみました!
こちらがメリット・デメリットのまとめになります!!
| 比較ポイント | 記帳代行 | 内製化 |
|---|---|---|
| 初期コスト | 低い(すぐに開始可能) | 高い(人材採用・システム導入) |
| 月額費用 | 10,000円〜100,000円程度 | 人件費・システム費用込みで高額 |
| 専門性 | 高い(プロによる対応) | 採用次第 |
| 情報のリアルタイム性 | 低い(月次報告が一般的) | 高い(随時確認可能) |
| フローカスタマイズ性 | 低い(業者に依存) | 高い(自社で決定) |
| 情報セキュリティ | 外部委託リスクあり | 社内管理で安全 |
| 品質の安定性 | 業者による差がある | 社内体制次第(体制が整えば安定) |
| 解約時の負担 | データ移行等で高負担 | なし |
| 上場準備対応 | – | 必須 |
じゃあ記帳代行と経理内製化、どちらを選ぶべき?
では記帳代行と経理内製化のどちらを選ぶべきでしょうか?企業規模の観点から、記帳代行と経理内製化の比較を考えてみます。

やはり経理内製化の最大のメリットは、自社の経営状況を素早く、タイムリーかつ詳細に把握できることですね…!!
ただしイチから始めるのはなかなか難しいので、経理内製化を支援してくれるアドバイザーに依頼するのがおすすめです!!
まとめ
記帳代行と経理内製化を比較してきましたが、長期的な企業価値向上の観点では経理を内製化していく必要があります。確かに記帳代行は初期コストを抑え、短期的な効率化を実現できますが、企業が持続的に成長し、競争力を維持していくためには、財務情報をリアルタイムで把握し、戦略的な経営判断を下せる体制の構築が不可欠です。
特に、デジタル化が進む現代において、経理業務は単なるコスト部門ではなく、企業の意思決定を支える戦略的パートナー(いわゆる攻めの経理)としての役割が求められています。上場を目指す企業であれば経理の内製化は必須条件ですし、そうでない企業においても、事業の透明性向上、内部統制の強化、ステークホルダーからの信頼獲得において、経理内製化のメリットは大きいものがあります。
ただし、記帳代行から内製化への移行は、適切な戦略と専門的な支援なしには困難を伴います。人材確保、システム選定、業務フロー設計、など、多岐にわたる専門知識が必要です。こうした移行プロセスを成功に導くためには、豊富な経験を持つ専門パートナーと共に、企業の成長段階に最適化された移行戦略を構築することが、確実で効果的なアプローチといえるでしょう。
バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!
記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!
ロジメイトの特徴
-
公認会計士による専門的なサポート
-
企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援
-
創業期からIPO準備企業まで幅広い実績
-
自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!