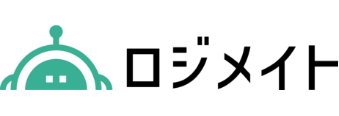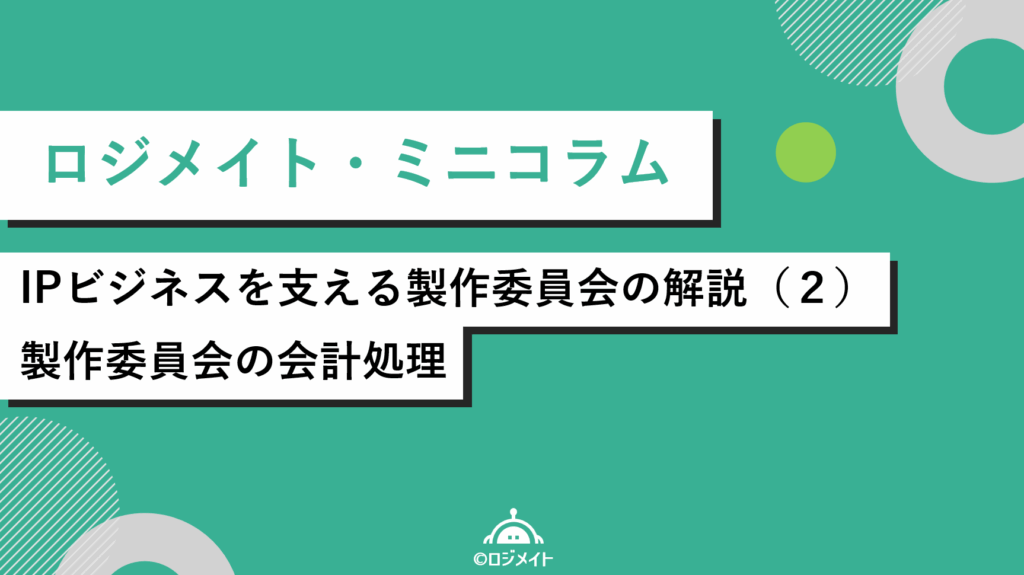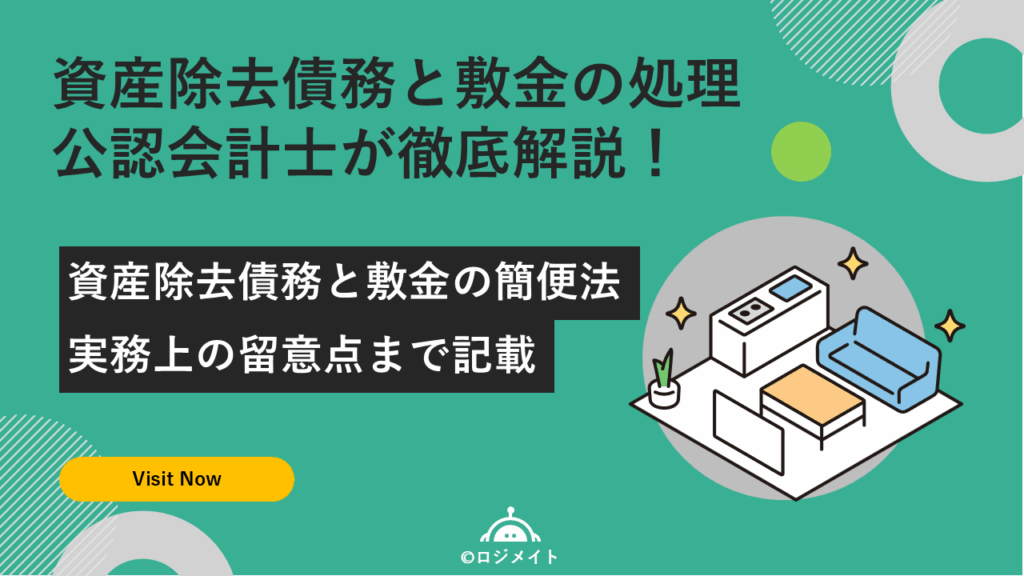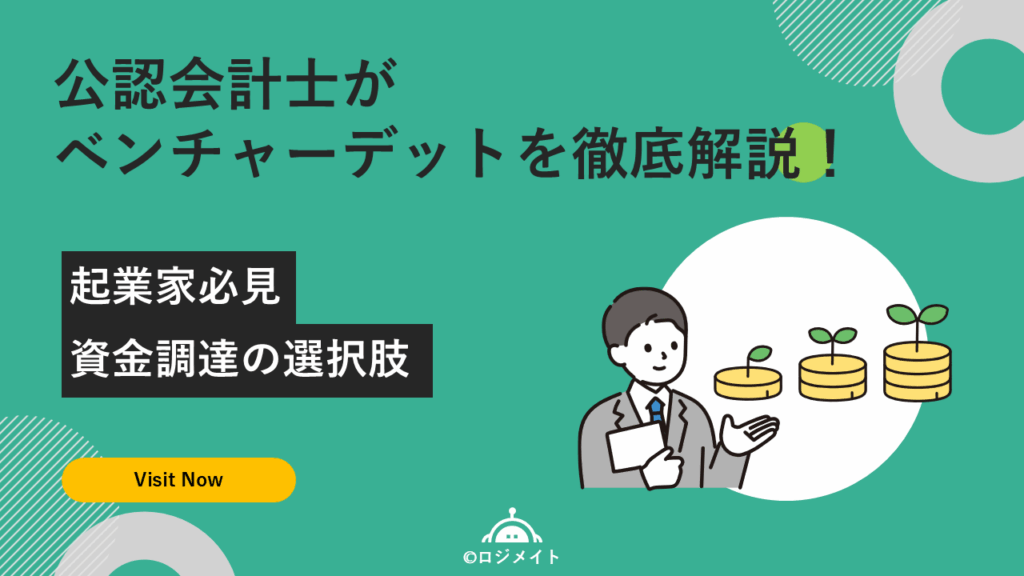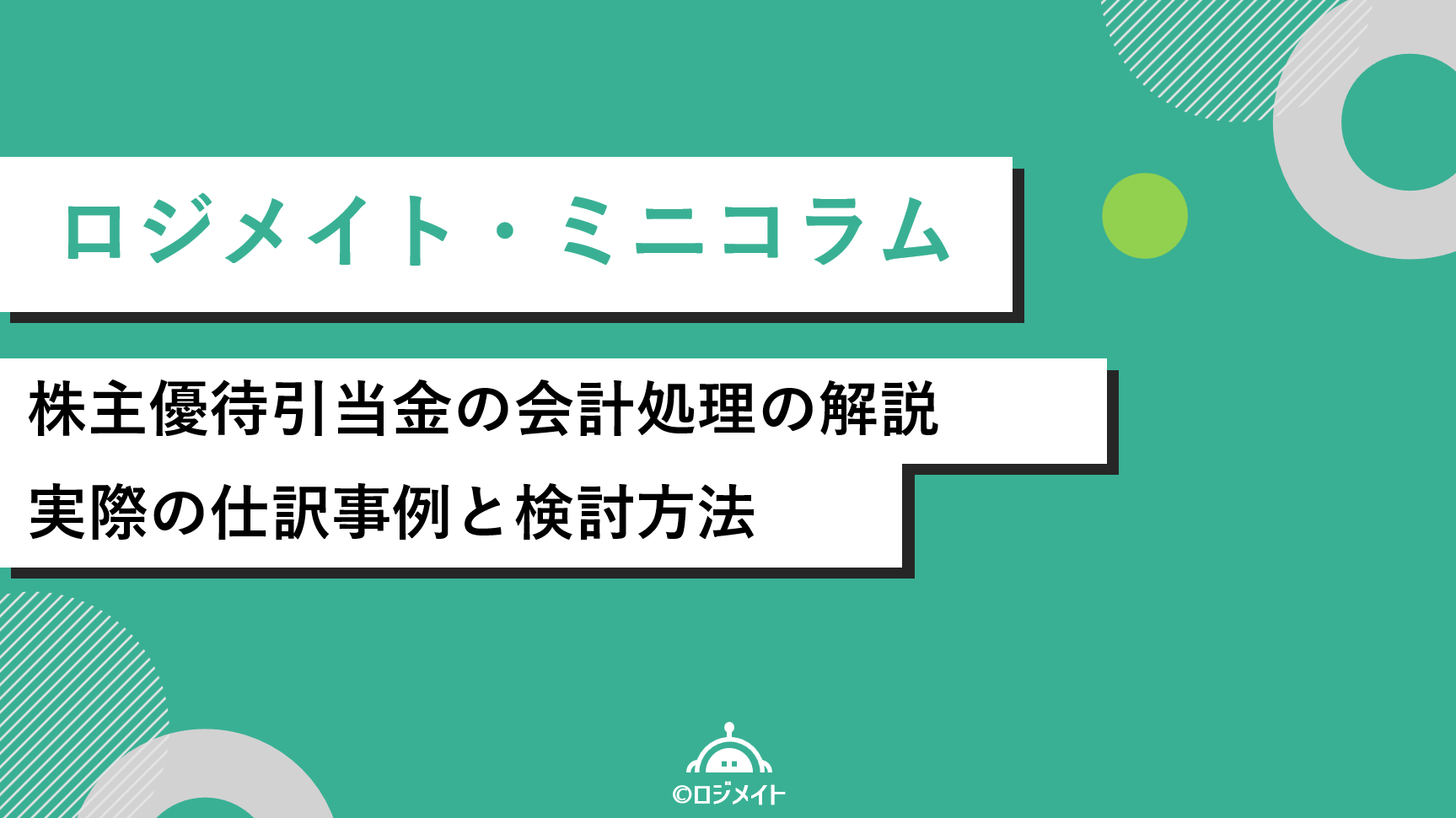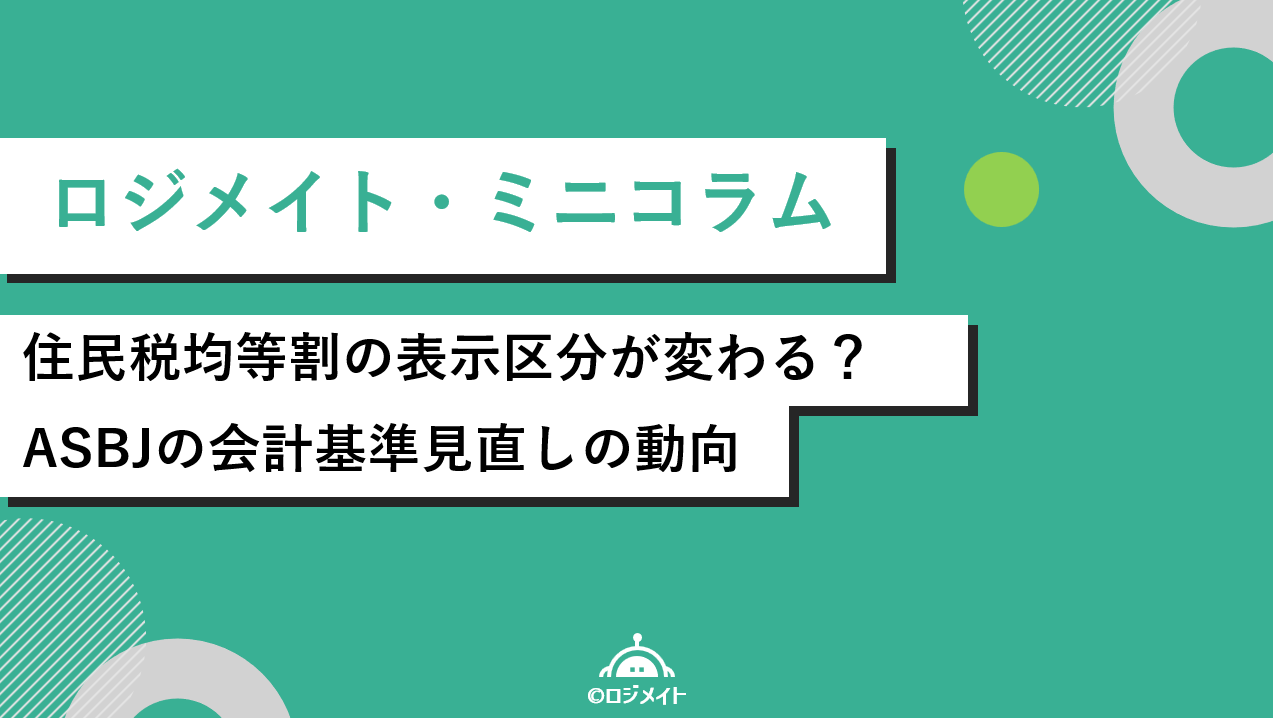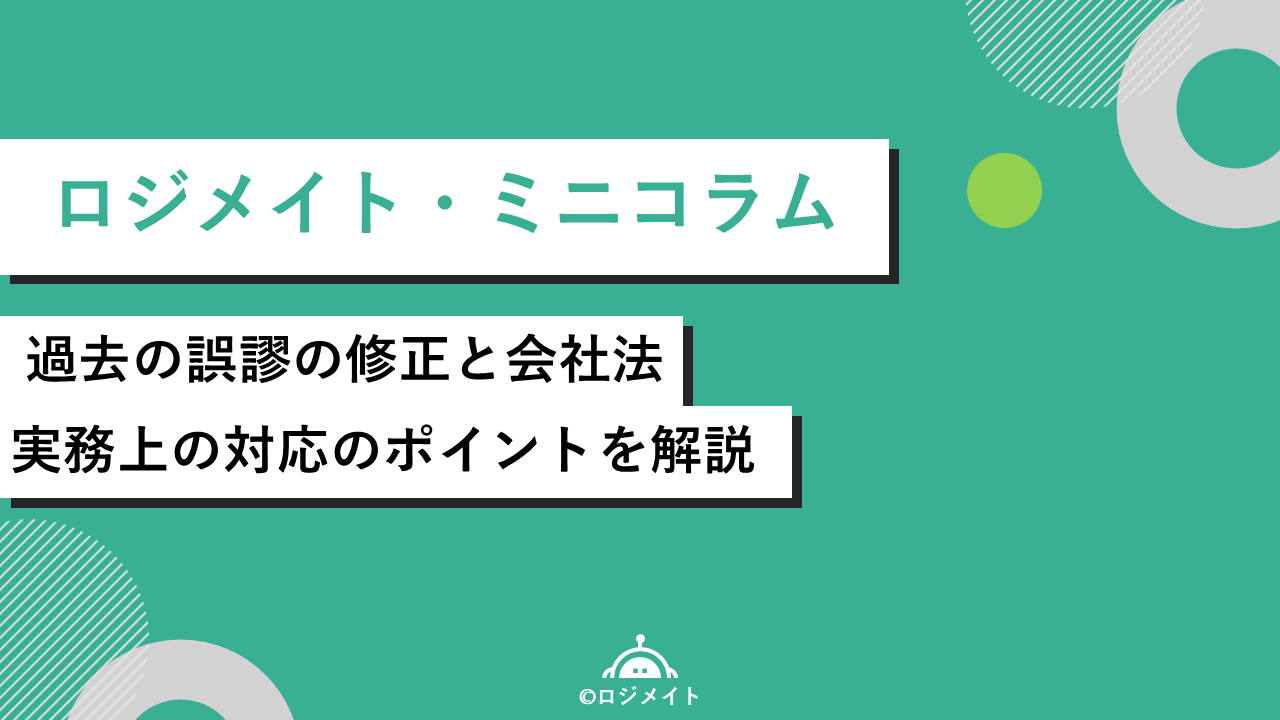制度解説_会計 財務関連
【2025年最新】新株予約権付融資(ベンチャーデット)の会計処理を徹底解説
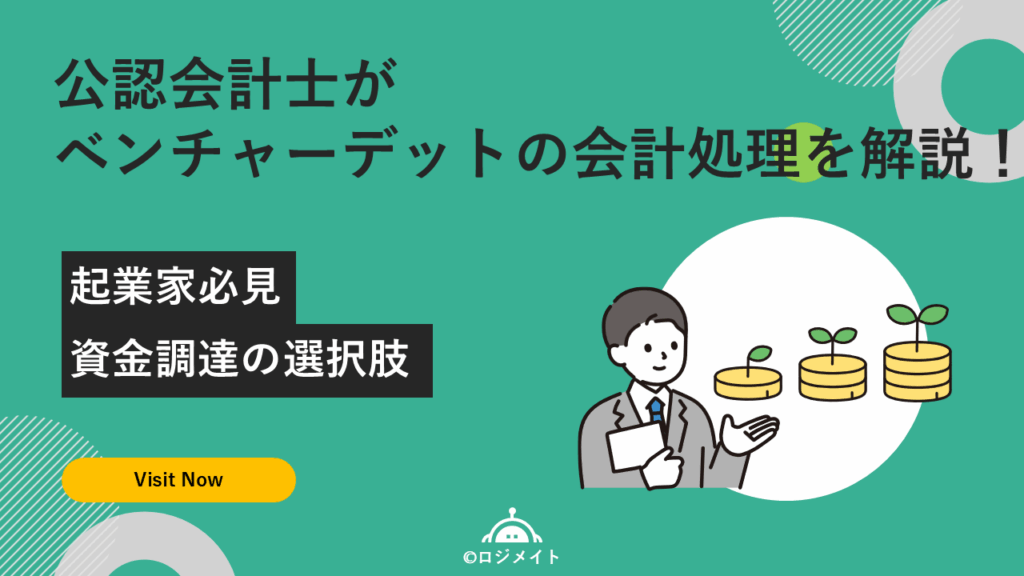

目次
Last Updated on 2025年9月5日 by ロジメイト編集部
【2025年最新】新株予約権付融資(ベンチャーデット)の会計処理を徹底解説
スタートアップ界隈で話題の新株予約権付融資、実際に導入を検討している企業も多いのではないでしょうか。エクイティとデットの中間的な性質を持つベンチャーデットの代表格として、多くの未公開企業が注目している資金調達手法です。
ところが、いざ会計処理となると「どう仕訳すればいいの?」と悩む経理担当者が後を絶ちません。従来のストックオプションとは全く異なる会計基準が適用されるため、知らずに間違った処理をしてしまうケースも散見されます。
そこで今回は、新株予約権付融資の会計処理について、実務で押さえておくべきポイントを中心に解説していきます。
新株予約権付融資(ベンチャーデット)の基本的な仕組み
新株予約権付融資とは何かを改めて整理しておきましょう。スタートアップ企業が金融機関等から融資を受ける際、同時に新株予約権も交付する資金調達スキームのことです。従来の新株予約権付社債における社債部分が、金銭消費貸借契約(普通の融資)に置き換わったものと理解するとわかりやすいでしょう。
この仕組みが注目される理由は、企業側から見ると、既存株主の株式希薄化を当面抑制できるからです。つまり、通常の増資と違って、新株予約権が実際に行使されるまでは新株発行されないためです。加えて、新株予約権を付与する代わりに通常の融資より低金利での資金調達が実現できます。
一方、金融機関側も融資による安定的な金利収入に加えて、将来的な株式売却益(キャピタルゲイン)の獲得機会を得られるというメリットがあります。

新株予約権付融資(ベンチャーデット)の詳細も記事にしています!
新株予約権付融資(ベンチャーデット)にはどの会計基準が適用されるのか
ここからが会計処理の本題です。新株予約権付融資で最初に理解すべきなのが、適用される会計基準の特定です。
多くの経理担当者が勘違いしやすいポイントなのですが、従業員向けストックオプションの会計処理とは完全に別物です。新株予約権付融資には「企業会計基準第10号『金融商品に関する会計基準』」が適用されます。
なぜストックオプション会計基準ではないのか?答えは複合金融商品だからです。融資(金融負債)と新株予約権が組み合わさった金融商品なので、金融商品会計基準の適用範囲となるわけです。
さらに詳しく分類すると、「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品」に該当します。これに対応するのが「企業会計基準適用指針第17号『払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理』」(以下、適用指針17号)です。
この適用指針17号では、払込資本を増加させる可能性のある部分(新株予約権)とそれ以外の部分(融資)の価値をそれぞれ認識できるなら、別個に会計処理することが合理的だと定めています。
結果として、未公開企業であっても、ストックオプション会計基準で認められている「単位当たりの本源的価値」での簡便処理は使えません。新株予約権の公正価値による評価が必須となります。
区分法による会計処理の実際
新株予約権付融資では「区分法」という処理方法を採用します。新株予約権の発行と融資の実行が同時に行われ、それぞれが独立して存在できるものだからです。適用指針17号に定められた「その他の新株予約権付社債」と同じ扱いになります。
区分法では、受け取った払込金額を融資部分と新株予約権部分に分けて処理します。金融商品会計基準に従った配分方法は2つあります。
ひとつめは、融資と新株予約権の払込金額または合理的な見積額の比率で配分する方法。ふたつめは、算定しやすい方の対価を先に決定し、払込金額から差し引いて残りを他方に配分する方法です。
実際の新株予約権付融資では、新株予約権付与により融資金利が優遇されているケースがほとんどです。この場合、適用指針17号の43項なお書きに従い、社債(借入金)と新株予約権のそれぞれの払込金額が経済的に合理的な額と明らかに乖離するときは、払込金額比率での配分は適当ではないとされているため、ふたつめの方法を採用することになります。
1億円
8,800万円
1,200万円
実務で重要な公正価値算定
払込金額の配分で最も重要なのが公正価値の算定です。実務では主に2つのアプローチが使われています。
アプローチその1:融資部分を先に算定
「新株予約権が付されていなかった場合に設定されたであろう純粋な借入金に対する金利」を使って、将来キャッシュフローを現在価値に割り引き、融資の公正価値を求める方法です。
実際に計算してみましょう。新株予約権付融資総額1億円、契約期間3年、契約金利年2.0%、市場金利(新株予約権なし)年5.0%の場合:
将来の元利合計を市場金利5.0%で割り引くと、融資の公正価値は約9,188万円となります。残りの812万円(1億円-9,188万円)が新株予約権の価値ということになります。
アプローチその2:新株予約権を直接評価(実務の主流)
新株予約権の公正価値を外部評価機関等により直接算定し、残額を融資部分とする方法です。実務では新株予約権を直接評価する方がよく使われています。
理由は明確で、まず「新株予約権なしの場合の金利」を金融機関に聞いても教えてもらえないことがほとんどだからです。また、外部評価機関による専門的な評価の方が監査対応もスムーズですし、特にIPO準備企業では監査法人から新株予約権の外部評価を求められることが多いという事情もあります。
新株予約権の評価には、ブラック・ショールズ・モデルが最も一般的に使われます。複雑な行使条件がある場合は二項モデル、さらに複雑な条件設定の場合はモンテカルロ・シミュレーションが用いられることもあります。
例えば、外部評価により新株予約権価値が1,200万円と算定された場合、融資部分は8,800万円(1億円-1,200万円)となります。
どちらを選択すべきか
IPO準備企業であれば、新株予約権の外部評価(アプローチ2)がほぼ必須です。まだIPOの予定がない未公開企業でも、金額の重要性が高い場合は外部評価の検討をお勧めします。企業の状況、監査法人の方針、金額の重要性などを総合的に考慮して判断しましょう。
(新株予約権なしの場合:5.0%)
融資部分:9,188万円
812万円(1億円-9,188万円)
(オプション評価モデル使用)
新株予約権:1,200万円
8,800万円(1億円-1,200万円)
取得時の仕訳処理
実際の仕訳例を見てみましょう。払込金額1億円の新株予約権付融資で、外部評価により新株予約権価値が1,200万円、融資部分が8,800万円と算定された場合:
この仕訳により、複合金融商品である新株予約権付融資が適切に区分して認識されます。決算処理で押さえるべきポイント
決算処理では、融資部分と新株予約権部分のそれぞれについて適切な処理が必要です。
融資部分の決算時処理
融資部分については実効金利法に基づく利息費用の計上を行います。ただし、実際の処理方法は企業の契約条件により異なるため、専門家による個別検討が不可欠です。
基本的な考え方として、新株予約権付融資では経済的実質を重視した会計処理が求められます。金融機関が新株予約権を取得する対価として融資金利を市場金利より低く設定しているため、会計上は本来支払うべき市場金利相当の利息費用を認識する必要があります。
前提条件を整理すると:
- ・新株予約権付融資総額:1億円
- ・融資部分の公正価値:8,800万円(外部評価により算定)
- ・契約上の金利:年2.0%(新株予約権付与により優遇)
- ・市場金利(同等リスクの通常融資):年5.0%
契約上の利息と会計上の利息費用には差異が生じます。契約上の利息(実際の支払額)は年200万円(1億円×2.0%)ですが、会計上の利息費用は年440万円相当(8,800万円×5.0%相当)となり、差額は年240万円相当です。
この差額240万円は、新株予約権の価値として既に認識済みの金額から実質的に賄われると考えられます。
決算時の仕訳例(12ヶ月経過時):
この仕訳の内容:- ・支払利息440万円:会計上の利息費用(8,800万円×5.0%×12/12)
- ・未払利息200万円:契約上の利息(1億円×2.0%×12/12)
- ・借入金240万円:融資部分の帳簿価額増加(実効金利法による調整)
重要な点として、具体的な決算処理方法については以下の理由により個別に専門家への相談が必要です。会計基準の解釈が複雑であること、企業固有の契約条件により最適な処理方法が異なること、特にIPO準備企業では監査法人と事前の合意形成が重要であることなどが挙げられます。
新株予約権部分の決算時処理
新株予約権部分については、金融商品会計基準に従った公正価値変動の評価が必要です。ただし、未公開企業では新株予約権の公正価値変動を把握することが困難な場合が多いため、実務上は取得時の公正価値を継続使用することが一般的です。
公正価値変動がある場合の例を示すと、取得時の新株予約権公正価値1,200万円が、決算時に1,500万円(外部評価等により算定)に上昇した場合:
ただし、多くの未公開企業では決算のたびに新株予約権評価を実施することは現実的ではないため、重要な事象(増資、事業環境の大幅な変化等)が発生した場合にのみ再評価を行うケースが多いというのが実情です。
IPO準備企業が特に注意すべき事項
IPO前の企業では、新株予約権付融資の会計処理が監査法人による審査の重要なチェックポイントとなります。
決算処理の継続性と合理性については特に厳格な審査が行われます。新株予約権の公正価値評価について、期間比較可能性を確保するため、評価方法や前提条件を変更する際には十分な合理的根拠が求められます。
外部評価機関の活用も重要な検討事項です。新株予約権の評価方法について、合理的かつ客観的な根拠に基づいた評価が必要なため、外部評価機関による評価の検討が重要となります。特に新株予約権の公正価値が重要性を持つ場合、複雑な行使条件が設定されている場合、IPO直前期における評価の客観性確保が必要な場合は、外部評価の実施が強く推奨されます。
税務処理との差異についても理解が必要です。税務上は会計処理とは異なる取扱いとなる場合があるため、税効果会計の適用や一時差異の認識について、税理士等の専門家と連携した適切な処理が求められます。
例として、会計上で新株予約権の公正価値1,200万円を認識した場合でも、税務上は権利行使時まで損金算入されないケースがあります。このような場合、将来減算一時差異として繰延税金資産の計上を検討する必要があります。
実務でよくある質問への回答
-
新株予約権付融資とストックオプションの会計処理はどう違うのですか?
-
適用される会計基準が根本的に異なります。ストックオプションには「ストック・オプション等に関する会計基準」が適用され、未公開企業では本源的価値による簡便的な処理が認められています。しかし新株予約権付融資は「金融商品に関する会計基準」が適用されるため、未公開企業であっても新株予約権の公正価値による評価が必要となります。
-
決算時に新株予約権の公正価値を毎期再評価しなければならないのでしょうか?
-
金融商品会計基準上は時価評価が原則とされていますが、未公開企業では実務上、毎期の再評価は困難な場合が多いのが現実です。重要な事象(大型増資、事業環境の大幅な変化、IPO準備開始等)が発生した場合にのみ再評価を行い、それ以外の期間は取得時の公正価値を継続使用することが一般的です。ただし、IPO準備企業では監査法人から定期的な再評価を求められるケースが多いため、事前に監査法人と評価頻度について協議することをおすすめします。
-
融資の公正価値算定と新株予約権の直接評価、どちらの方法を選択すべきでしょうか?
-
実務では新株予約権の外部評価による直接算定の方が一般的に採用されています。「新株予約権なしの場合の市場金利」の特定が困難であること、外部評価による客観性の確保ができること、IPO準備企業では監査法人から外部評価が求められることが多いことなどが理由として挙げられます。特にブラック・ショールズ・モデル等の確立された評価手法により、合理的な価値算定が可能です。ただし、評価コストや企業の状況を総合的に勘案して選択することが重要です。
-
転換社債と新株予約権付融資の会計処理に違いはあるのですか?
-
基本的な考え方は類似していますが、いくつかの相違点があります。転換社債は社債と新株予約権の組合せであるのに対し、新株予約権付融資は融資(借入金)と新株予約権の組合せです。どちらも複合金融商品として区分法が適用されますが、負債部分の性質(社債 vs 借入金)が異なるため、利息計算方法等に差異が生じる場合があります。また、転換社債の場合は転換時に社債が消滅しますが、新株予約権付融資では権利行使後も融資の返済義務は継続します。
-
新株予約権が行使された場合の会計処理はどうなりますか?
-
新株予約権が行使された場合、適用指針17号に従い、新株予約権残高と払込金額を資本金及び資本準備金に振り替えます。具体的には、新株予約権の対価部分は資本準備金に振り替えられることになります。融資部分については新株予約権の行使とは無関係に返済義務が継続するため、借入金残高に変動はありません。また、権利が行使されずに権利行使期限が到来した場合は、新株予約権残高を利益として処理します。
-
決算時の利息費用はどのように計算すればよいのですか?
-
融資部分の利息費用計算は複雑な会計論点を含んでいます。基本的な考え方として、契約上の利率ではなく「新株予約権が付されていなかった場合に設定されたであろう市場金利相当」で利息費用を認識する必要があるとされていますが、具体的な処理方法は各企業の契約条件や監査法人の判断により異なります。実務上は、公認会計士等の専門家に相談して、適切な処理方法を決定することを強く推奨します。特にIPO準備企業では、事前に監査法人との合意形成が重要です。
押さえておきたい実務のポイント
新株予約権付融資の会計処理では、従来のストックオプション会計とは全く異なる専門的な知識が求められます。金融商品会計基準に基づく区分法の適用、新株予約権の公正価値評価、そして適切な仕訳処理の実行が、正確な財務報告のために不可欠となります。
スタートアップ企業の経理担当者にとって、この新しい資金調達手法の会計処理について十分な理解を深めることは重要です。必要に応じて公認会計士や税理士などの専門家との連携を図ることで、将来のIPO準備においても円滑な監査対応が可能となるでしょう。
バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!
記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!
ロジメイトの特徴
-
公認会計士による専門的なサポート
-
企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援
-
創業期からIPO準備企業まで幅広い実績
-
自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!