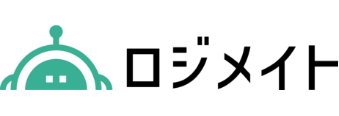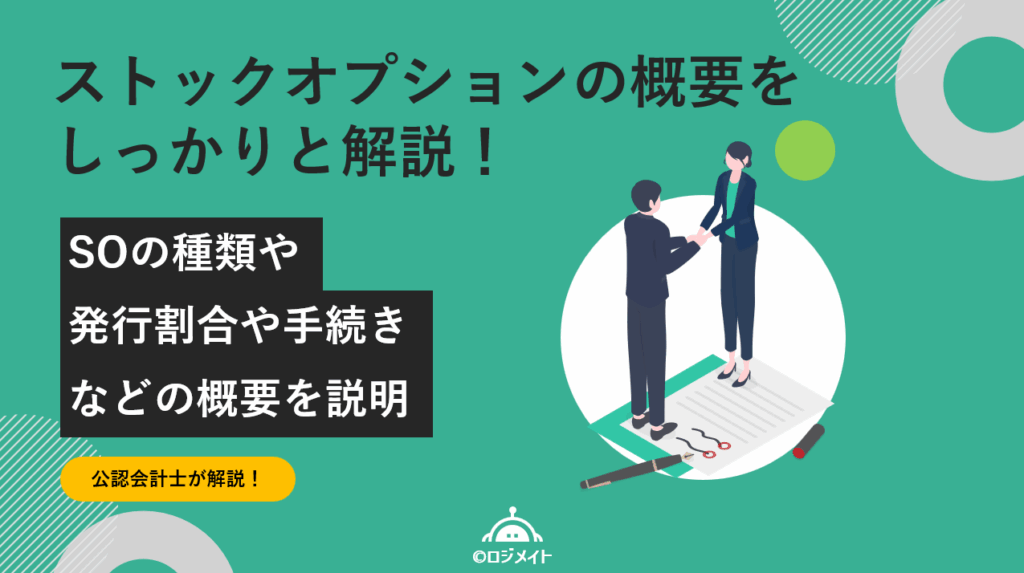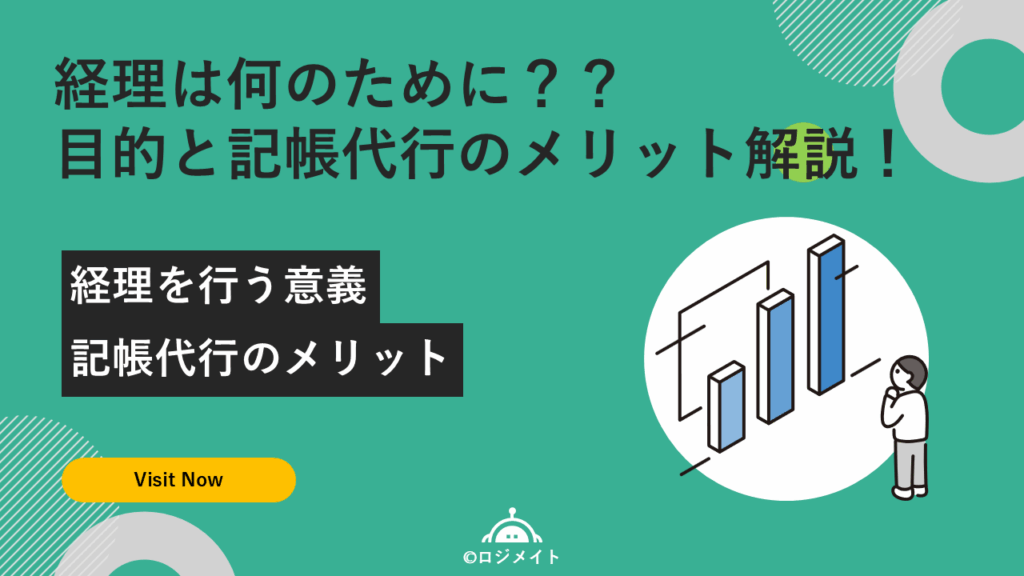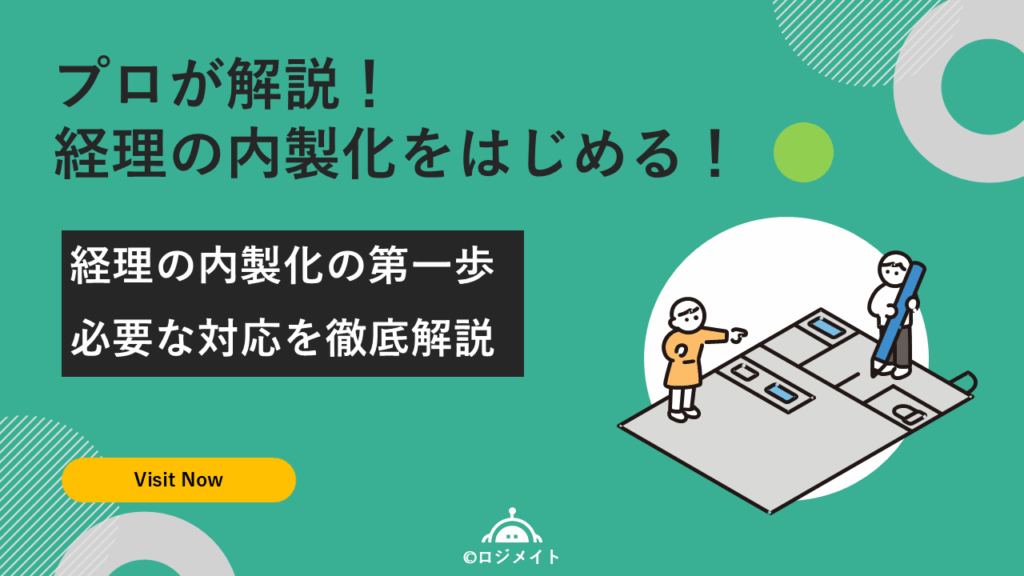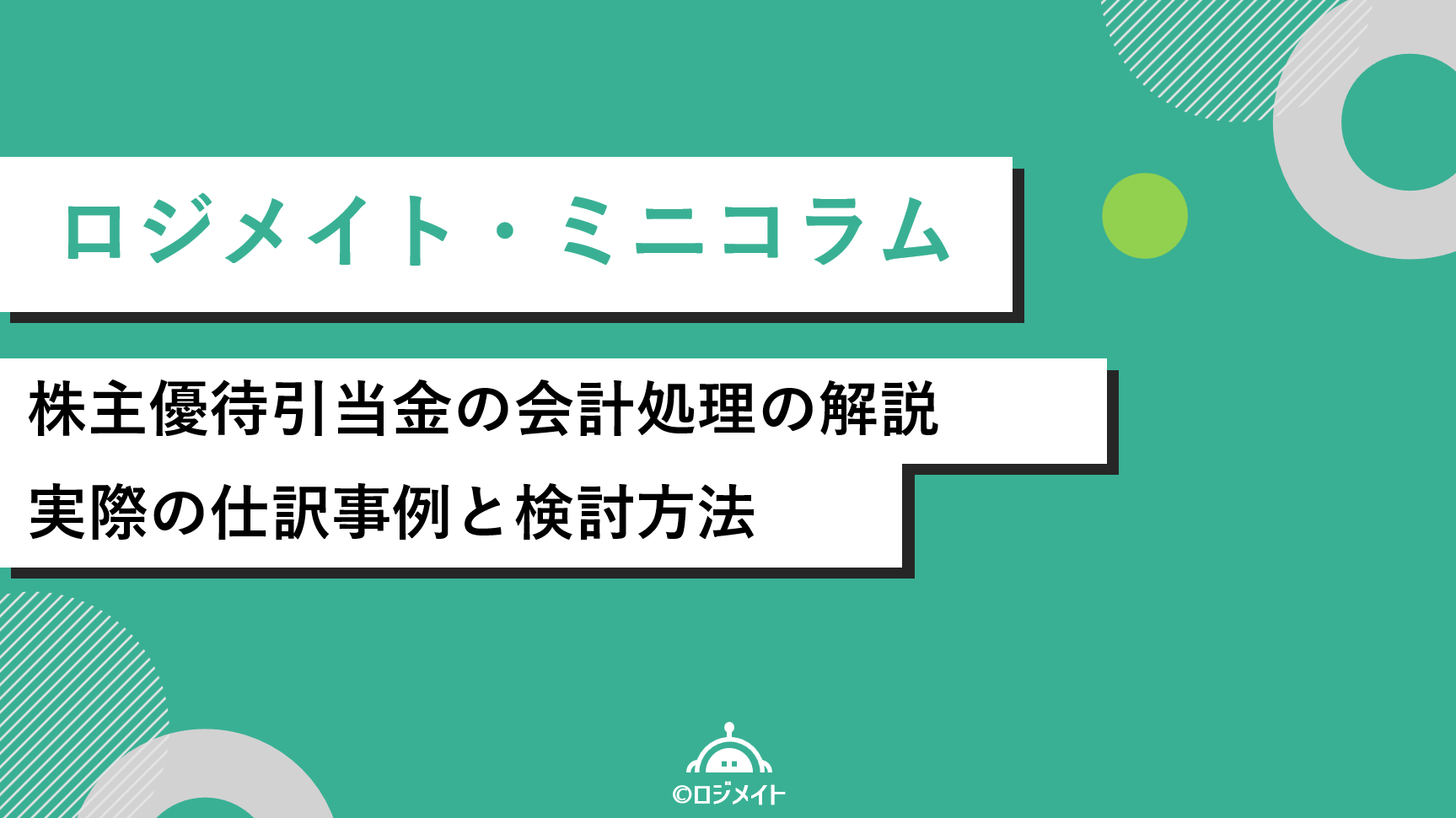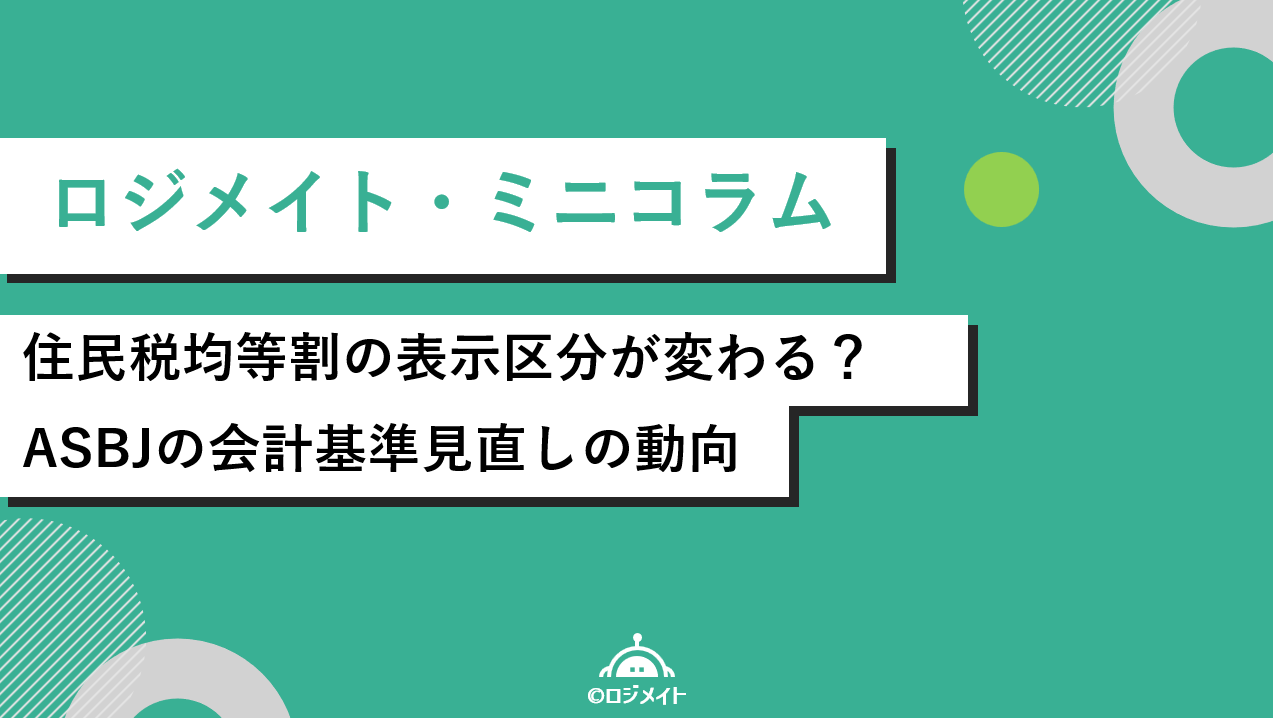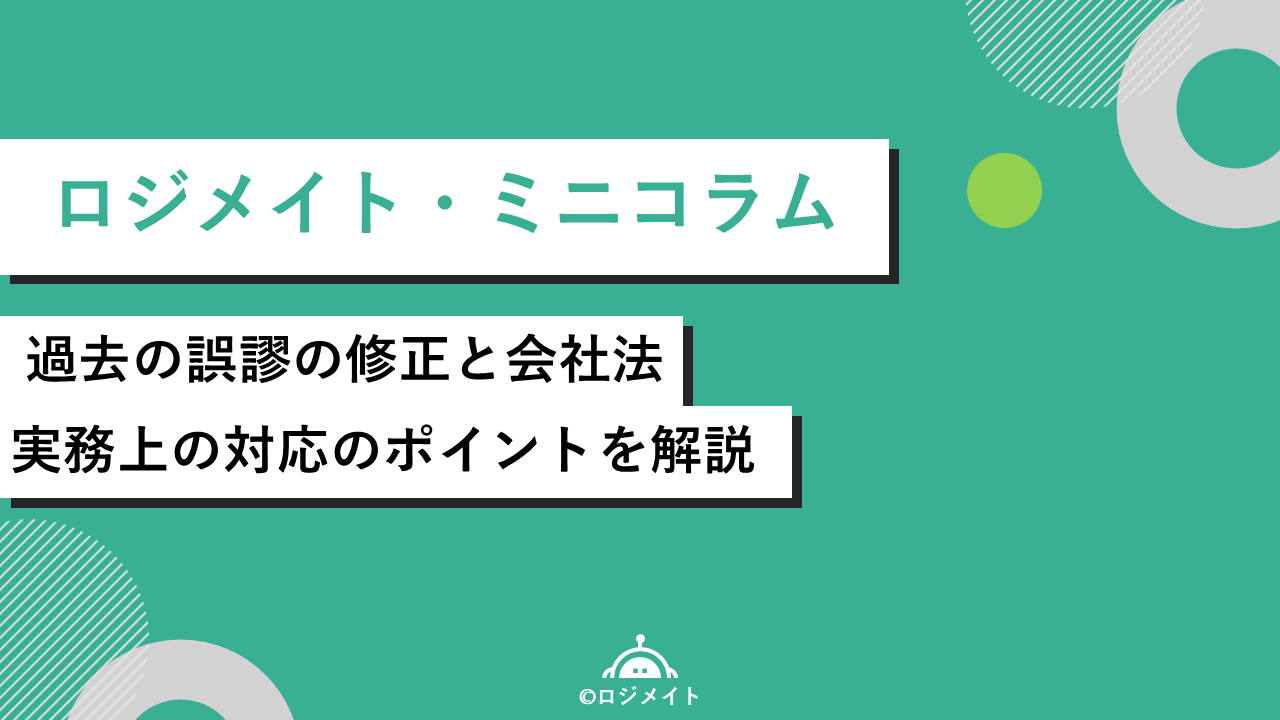バックオフィス支援
【経理のプロが解説】記帳代行の解約で失敗しない方法|公認会計士が教える実践ノウハウ
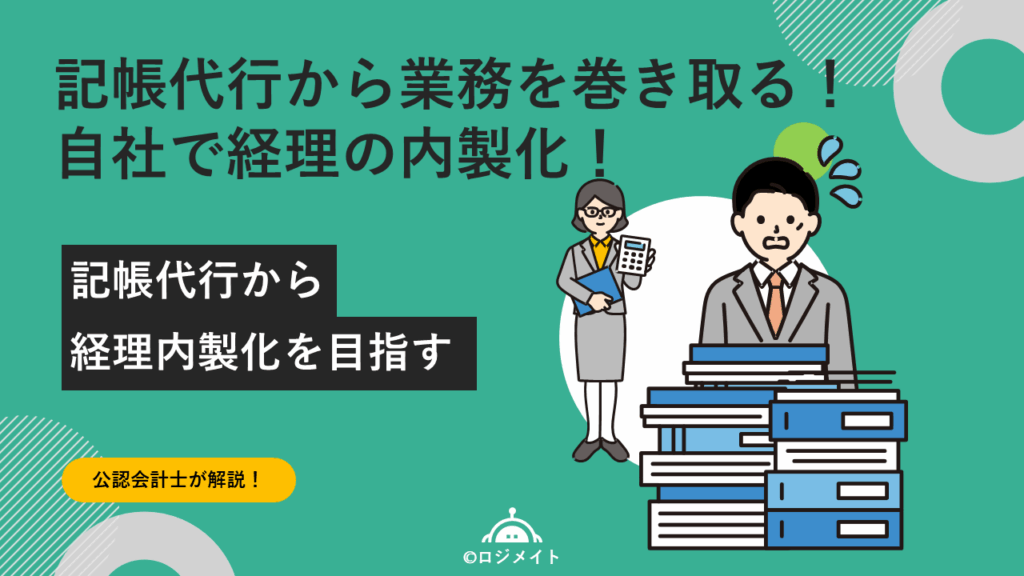

目次
Last Updated on 2025年8月5日 by ロジメイト編集部
【経理のプロが解説】記帳代行の解約で失敗しない方法|公認会計士が教える実践ノウハウ
売上の規模が大きくなり、従業員の数も増えてくると、多くの経営者が「そろそろ経理は自社でやるべきかな」と考え始めます。業務の規模拡大に伴い、障壁になってくるのが業務を依頼していた記帳代行からの業務の巻き取り。私も以前勤めていた会社で記帳代行業者から経理業務を巻き取ったことがありますが、中々に骨が折れました。。。
記帳代行からの業務移行経験を踏まえ、記帳代行から自社での経理の内製化への移行を検討している企業の皆さんに、契約終了時の具体的な手順とトラブル回避のコツをお伝えします。

私自身、まだ経理の経験も浅い頃のお話です。
想像以上に大変でした。。。
いつ経理を内製化を決断すべきか?現場から見た兆候
経理を内製化すべき状況である場合、経験では以下のような兆候があります。いずれも、経営上の必要性に迫られたものになります。
月次決算が遅すぎて、経営判断が後手に回っている
「先月の数字、まだ出てないの?」
社長からこんな言葉が出始めたら、黄色信号です。記帳代行を使っていると、どうしても月次決算は翌月の中旬以降になりがち。私が経験した会社では、月末締めの数字が出てくるのが翌月20日頃でした。
でも考えてみてください。20日も経ってから先月の業績を知って、果たして迅速な経営判断ができるでしょうか?特に市場環境が目まぐるしく変わる今の時代、この2〜3週間の遅れは致命的になることもあります。
記帳代行の請求書を見て「これだけ払うなら社員を雇えるのでは?」と思い始めた
月間の仕訳数が1,000件を超えてくると、記帳代行の月額料金は10万〜20万円になることも珍しくありません。年間にすると120万〜240万円。決算業務や年末調整などのオプションを含めると、300万〜400万円に達することもあります。
「これだけあれば、経理担当者を1人雇えるじゃないか」
そう思ったことはありませんか?しかも、自社の経理担当者なら記帳だけでなく、資金繰り表の作成や予算実績管理、さらには経営分析などの業務まで担ってもらえることが可能です。また、長くいてもらうことで、会社を理解した記帳や、ノウハウの蓄積が可能になります。同じコストでより多くの価値を生み出せるわけです。
また、記帳代行では「今すぐ残高を教えて」と簡単に聞くのにもハードルがあります。
日々の経営では「今の数字」をすぐに知りたい場面が多いと思います。大型案件の受注可否を即断したいとき、設備投資のタイミングを計りたいとき、新規採用の判断をしたいとき。リアルタイムの財務情報がないと、どうしても判断が遅れがちになります。
記帳代行業者に依存しすぎて、自社に経理ノウハウが全くない
長年記帳代行に頼っていると、社内に経理の知識を持つ人が誰もいない状態になってしまいます。私が知っているケースでは、5年以上同じ記帳代行業者を使い続けた結果、社内に処理がわかる人間がいなくなってしまい、記帳代行業者がしたミスを気づけなかったということがありました。
万が一、記帳代行業者が廃業したら?記帳代行側の担当者が急に変わって引き継ぎがうまくいかなかったら?価格を大幅に値上げされたら?
こうしたリスクに対して、全く対抗手段がない状態は危険です。経理は会社の基幹業務であり、ある程度は自社でコントロールできる体制が必要だと考えられます。
そろそろIPOを視野に入れ始めた
上場を目指す企業にとって、経理の内製化は避けて通れない道です。
監査法人は必ずこう聞いてきます。「経理体制はどうなっていますか?」
このとき「全部外注です」では話になりません。J-SOXに対応した内部統制システム、45日以内の決算開示、監査対応できる経理体制。これらはすべて、自社に経理機能がないと実現が困難かと考えられます。
また、IPOを目指さない企業でも、内部統制の強化は重要です。不正防止、ミスの早期発見、業務の効率化。これらはすべて、自社で経理を行うことで初めて本格的に取り組めるようになります。

経理を内製化する必要性を感じる=会社が成長してきている
ということですね!!
契約終了の準備は思った以上に大変!必要な手続きを徹底解説
経理の内製化を決意したら、次は記帳代行業者との契約終了に向けた準備です。
1. まずは契約書を引っ張り出してきて、じっくり読み返す
まずは当然ですが、記帳代行業者との契約を読み返しましょう。特に注意すべきは以下のポイントです。
注意するポイント
自動更新条項に注意
多くの記帳代行契約には、こんな一文が潜んでいます。
「本契約は、期間満了の3ヶ月前までに、いずれかの当事者から書面による終了の申し出がない限り、同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとする」
見落としがちなんですが、こちら要注意です。私の知り合いの会社では、2月に「4月から自分たちでやります」と伝えたら、「もう自動更新されてますよ」と言われてげんなりしたそうです。結局、違約金を払うはめに…。
解約は必ず書面で(メールじゃダメな場合が多い)
「解約の申し出は書面により行うものとする」
この一文も見逃せません。最近はメールでのやり取りが当たり前になっていますが、契約解除となると話は別。内容証明郵便で送るのが一番確実です。「言った言わない」のトラブルを避けるためにも、証拠を残しておきましょう。
契約が終わっても続く義務がある
契約書の最後の方に「残存条項」という項目があるかと思います。これは契約終了後も効力が続く約束事のことです。
他にも、もし記帳ミスが後から見つかった場合の損害賠償責任や、作成した帳票類の著作権の扱い、データの削除義務なども残存条項に含まれることがあります。
例えば秘密保持義務。「契約終了後3年間は、業務上知り得た情報を他言してはならない」なんて書いてあることが多いです。お互いの会社の重要情報を扱っているわけですから、これは当然といえば当然ですね。
「契約が終わったからもう関係ない」では済みません。どんな義務が残るのか、しっかり確認しておきましょう。

テンプレートかと思ってよく読まないと、思わぬ損をしちゃいますね。。。
2. データ・資料の引き継ぎは、想像以上に時間がかかる
「データはCSVで渡しますから、簡単ですよ」
記帳代行業者からこう言われて安心していませんか?
必要なデータは想像以上に多く、整理には時間がかかります。
まず、何を引き継いでもらうか、リストアップから始めましょう。最低限必要と考えられるのは下記になります。
必要なデータ・書類
会計の基本データ
-
過去全期間の仕訳データ(これなしでは記帳を追跡不可能になります)
-
上記の総勘定元帳と補助元帳(取引の詳細を追いやすくなるように)
-
月次・年次の試算表
-
過去全期間の決算書一式
-
固定資産台帳(今までの減価償却計算を追跡するのに)
税務関係の書類
-
担当してもらった全期間の各種申告書控え(法人税・地方税・消費税・事業所税等)
-
担当中、提出した届出書の控え(青色申告承認申請書など)
-
担当してもらった全期間の源泉徴収簿や支払調書
労務関連のデータ(給与計算も担当されていた場合)
-
過去全期間の給与台帳
-
従業員情報のマスタ
-
社会保険関係の書類
-
各種税金(所得税・住民税)の通知書
「え、こんなにあるの?」と思われるかもしれませんが、上記のデータ・書類でもまだ一部です。基本的には記帳代行から提出してもらった資料は、全て揃っているのを確認するようにしましょう。後で「あのデータもらってない!」となっても、対応してくれない場合もあります。

上記のデータが欠けていると、後で本当に、本当に苦労します。。
確実に手に入れましょう…!!
3. 紙の書類も忘れずに返してもらおう
デジタルデータだけでなく、紙の書類の返却も重要です。特に原本は、監査手続や税務調査などで必要になることがあります。記帳代行に提出した紙の資料は必ずすべて回収するようにしましょう。
返却が必要な紙の書類
経理関係
-
全ての領収書と請求書(できれば年度別・月別にファイリングされた状態で)
-
通帳やクレジットカードの明細
-
各種税金の納付書
契約書類
-
売上や仕入取引に関する取引基本契約書
-
リースに関する契約書
-
オフィスなどの賃貸借契約書
-
金融機関との各種契約書(金銭消費貸借契約書)
労務関連のデータ(給与計算も担当されていた場合)
-
過去全期間の給与台帳
-
従業員情報のマスタ
-
社会保険関係の書類
-
各種税金の通知書

請求書や領収書といった原本がないと、税務調査でペナルティを受けてしまう可能性あり!!
上記の書類もしっかり返却してもらいましょう!
4. 返却時の注意点
ただ「返してください」では不十分。後でトラブルにならないよう、以下の点に注意しましょう。
返却時の注意点
-
詳細な返却リストを作る:「令和○年度に提出した領収書」などある程度具体的に
-
できれば現物を確認:本当に全部あるか、目で見て確認
-
受領書を必ず作成:トラブル回避のため、お互いにサインして、1部ずつ保管

紙の書類ですが、「全部返した」「いや、受け取ってない」というトラブルは意外と多い。。。
面倒でも、きちんと証拠を残しておきましょう。
5.「暗黙知」を文書化してもらうのが大事
数年間も記帳代行を使っていると、記帳代行業者だけが知っている「うちの会社のやり方」がたくさん蓄積されています。業務を処理するうえでの「暗黙知」を引き継いでもらえないと、仕訳処理を追跡する際とても苦労します。
例えばですが、
日常の処理ルール・不明な残高について
- 「交際費と会議費、どう使い分けてました?」
- 「この取引先の請求書、いつも消費税の端数処理が特殊でしたよね?」
- 「どうしてこんなに短期借入金が多いんですか?」
- 「預り金の残高が給与明細の一覧と一致しないんですが、どうしてですか?」
イレギュラーな処理の方法
- 「返品があったとき、どう処理してました?」
- 「為替差損益って、どのタイミングで計上してました?」
- 「過去に貸倒れになった取引、どう処理しました?」
上記のような「暗黙知」は契約書やマニュアルには書いていない、でも自社で経理を内製化する際に必要になってくる情報です。契約を解除する前に、必ず聞き出しておきましょう。
なお、こうしたイレギュラーな処理は、実際に帳簿を詳しく見ていかないと発見できないことも多いです。
ですので、自社で経理をしていく期間、記帳代行業者に処理についていつでもヒアリングできるよう、できれば1〜2ヶ月は「並走期間」を設けるのが推奨されます。
例えば、4月から完全移行するなら:
- 3月:自社がメインで処理、記帳代行業者がチェックとアドバイス
- 4月:完全に自社で処理、追加で質問があればその都度確認
このような形で段階的に移行すれば、スムーズにバトンタッチできます。

不明な処理や残高はしっかり特定しないと、
のちのちどうしようもなくなってしまいますね。。。
必要なデータ移行|自社で経理を始める第一歩
必要なデータを入手したら、早速自社の会計システムに記帳していきましょう。この時、以下のポイントに留意いただければと思います。
データの移行は期首残高の確定から始める
データ移行では、期首残高の確定から始めることが重要です。記帳代行業者がやっていた次の月から記帳していくといったような、会計期間の途中から、自社で記帳しようとすると大抵上手くいきません。以下のような失敗パターンがあります。
失敗パターン
-
途中から自社で経理するようした結果、期末に不明残高が発覚した。
-
期首残高の内訳がわからないまま記帳し、残高明細上マイナスの取引先・補助科目が出てきてしまった。
-
債権債務の消込がうまくいかず、残高がぐちゃぐちゃになった。

記帳代行業者によってはそもそも取引先・補助科目の残高がぐちゃぐちゃになってたり。。。
面倒ではありますが、期首のBS残高から確認していきましょう!
過去の記帳は無理に計上しようとしない
上でも書きましたが、そもそも記帳代行業者の記帳方法が少し特殊だったり、場合によっては間違って至ります。そのような状況の中、無理に記帳代行業者が行った仕訳を移行しようとすると、かえって巻き取りに時間がかかってしまう場合もあります。
会計処理や税務処理には、一定の正解が存在するため、そのような場合は過去の記帳は無視し、ゼロベースで記帳方法を自社で考えていくのが手っ取り早かったりします。
もちろん過去との処理の継続性は考慮もしなければなりませんが、自社で経理を行っていく以上、自社でルールを決めていくといった対応が最終的には効果的だと考えています。

会計処理の「正解」は知識がないとわからないのが経理の難しいところですね。。
会計処理の「正解」がわからず苦戦するのが想定される場合、専門家の利用がおすすめです!
実際にあったトラブル事例(これは他人事じゃない!)
次に、実際に起きたトラブル事例をご紹介します。
事例1:自動更新の罠にはまり、違約金120万円
A社の話です。3月決算の会社で、「4月から自社でやろう」と2月に決定。すぐに記帳代行業者に連絡したところ…
「申し訳ございませんが、契約書では3ヶ月前の通知が必要となっております。12月末までにご連絡いただかないと自動更新されてしまうんです。すでに来期の契約は確定しています」
結果、違約金として月額料金の6ヶ月分、約120万円を支払うことに。

大前提、契約書はよく読み、不明な点は解消してから締結しましょう。。
事例2:領収書の紛失で、税務調査時に50万円の追徴
B社。記帳代行業者から書類を返却してもらった後、税務調査が入りました。
調査官:「3年前の○月○日の領収書を見せてください」
B社:「え?ありません…」「業者さん、御社にあると思うので返してください!」
業者:「すべて返却済みです」
結局、その経費は否認され、追徴税額と延滞税で約50万円の支払いに。

返却した・してない問題は本当にあるある。。
特に高額な取引の原本(契約書・請求書・領収書)は、確実に収集しておきましょう。。
事例3:「一般的な処理」の罠
C社の話です。記帳代行業者からは「すべて一般的な処理なので、特別な引き継ぎは不要」と言われていました。
でも、いざ始めてみると…
- 給与仕訳の計上方法がよくわからない
- 共通費の配賦基準が不明(相談して決定した内容と整合しない)
- 過去の税務調査での指摘事項がわからない
結局、当該業者に追加料金を払って一からヒアリングすることに

「一般的」でもどこかに特殊な処理はあります。
経理処理についても必ず詳細な引き継ぎを。
契約終了通知のテンプレート
ここまでできれば、契約終了の通知を送りましょうです。以下、実際に使えるテンプレートをご用意しました。
契約終了通知のテンプレート
令和○年○月○日
株式会社○○記帳代行サービス
代表取締役 ○○ ○○ 様
契約解除通知書
拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
長年にわたり、弊社の記帳業務にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。
さて、弊社は組織体制の見直しに伴い、経理業務の内製化を進めることといたしました。
つきましては、貴社との間で締結しております記帳代行業務委託契約(契約締結日:令和○年○月○日)を、契約書第○条の規定に基づき、下記の通り解除させていただきたく、ご通知申し上げます。
記
1. 契約解除日:令和○年○月○日
2. 解除理由:今後、経理体制を構築し、自社にて経理を行うため
3. 引き継ぎ事項:
(1) 会計データの引き継ぎ(過去全期間)
(2) 証憑書類の返却
(3) 業務処理方法の文書化
※詳細は別途ご相談させていただきます
4. 並行処理期間:令和○年○月〜○月(2ヶ月間)
以上
なお、契約終了後も秘密保持義務等、契約書に定められた残存条項については、引き続き遵守いたします。
長年のご支援に改めて感謝申し上げるとともに、円滑な引き継ぎにご協力いただけますよう、お願い申し上げます。
敬具
株式会社○○
代表取締役 ○○ ○○
[印]
ポイントは以下となります。
-
感謝の気持ちを示す(今後も何かでお世話になるかも)
-
解除の根拠条文を明記する
-
引き継ぎ事項を具体的に書く
-
残存条項への言及を忘れない

最後は円満に終わりましょう!!
まとめ|準備さえしっかりすれば、後は根気
記帳代行からの脱却は、企業が成長していく上で必要な一歩です。確かに大変な作業ですが、きちんと準備すればスムーズにいきます。復習ですが、以下ポイントです。
-
早めの準備:最低でも3ヶ月前から動き始める
-
契約内容の確認:特に解約条件と残存条項は要チェック
-
データと書類の確実な引き継ぎ:リストを作って、漏れをなくす
-
円満な関係維持:将来、また協力が必要になるかも
最後に、記帳代行業者も、皆さんの会社の成長を支えてくれた大切なパートナーです。感謝の気持ちを忘れずに、お互いにとって良い形で契約を終了できるよう心がけましょう。
こういった引継ぎ作業ですが、時には過去の書類の山をあさったり、Excelをガチャガチャ集計して残高を調査しなければなりません。
自社経理への移行は確かに大変ですが、それ以上の価値があります。リアルタイムで数字が見える、経理ノウハウが社内に蓄積される、内部統制が強化される。これらはすべて、会社のさらなる成長につながります。
ロジメイトは、こういった記帳代行業者からの巻き取りも対応してます!!
お困りの際は、弊社に是非お声がけください!!
バックオフィス業務でお困りなら「ロジメイト」へ!
記帳業務を含むバックオフィス全体の課題解決をお考えでしたら、ロジメイトをご検討ください。

ロジメイトは、経験豊富な公認会計士がリードする総合的なバックオフィス支援サービスです。記帳代行か内製化かの判断から、最適なシステム選定、業務フロー設計、運用サポートまで、企業のフェーズに合わせて包括的にサポートいたします!!
ロジメイトの特徴
-
公認会計士による専門的なサポート
-
企業ニーズに合わせた最適なSaaS選定・運用支援
-
創業期からIPO準備企業まで幅広い実績
-
自走運用までの徹底したサポート体制

我々が丁寧にサポートいたします!ぜひお問い合わせください!!